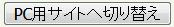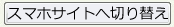英文読解から入試まで 完全マンツーマン指導
塾長のコラム 2020年5月20日 入試和文英訳⑤ 2020東北大学
 |
 |
|
入試和文英訳⑤ 2020東北大学 |
||
2020年5月20日 (動詞 claim について 20200923 に加筆) 皆様、KVC Tokyo 英語塾 塾長 藤野 健です。 和文英訳の問題を<解読>してみよう、のコラムの第5回目です。 入試英文添削の時と同じく、完成形?に至る塾長の考え、迷いなど思考のプロセスをご覧ください。他ではちょっと見られない企画だろうと思います。 以下参考サイト:https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ |
||
 |
 |
旧東北帝国大学附属図書館閲覧室(東北大学史料館)
http://www.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/shiteidb/image/3036.jpg
http://www.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/shiteidb/c03036.html
大正15年の鉄筋コンクリート造建築
 |
 |
|
誰もまだ到達したことのない未知の世界を究めてみたい、美術、音楽などの芸術の世界から芸能の世界まで、そんな純粋な要求が文化を支えている。サイエンティストと呼ばれる一群の人々は、この知の限界に挑戦することを楽しむ人々である。その成果だけではなく、知の限界への挑戦のプロセスそのものを含めて、それが「文化」なのだ。「文化」には役に立つ、立たないの区別は意味を持たない。(東北大2020年前期 )【和訳の基本戦略】*サラリと書かれた感じの一見伸びやかに見える日本語であり、平易な表記ながらも知性が感じられます。但し、各々の文章内容の連続性が悪く、次の文章に行く度に思考の相転移が起き、ぶっきらぼうな雰囲気も多少覚えます。これはのちに触れますが、階調 gradation の伴わない、悉無的表現、断定が続く硬い文章だからです。*美術などの「世界」に於いて誰も到達したことの無い「世界」を究めるならば、それは自分たちが所属する「世界」とは別の「世界」となります。ここでは自分たちが属する世界の中で到達したことのない領域に踏み込みたい、到達したいとのことでしょう。この様に、煮詰まっていない記述が含まれています。まぁ、感覚的には言いたいことが分かるものの、細部を詰めるとほころびが出る文章ですね。推敲の不足するエッセーですが、この様な思いつくままに述べる内容でしたら1日に原稿用紙数十枚はサラリと書けるだうと想像もします。但し、この程度では後世の人達からは忘れ去られるでしょう。*エッセー風の和文によく見られる事象ですが、日本語固有の通りの良いエエカッコシ文化人用語が配列され、持論が展開されるのですが、吟味すると正確には何を表現したいのかの曖昧性を含み、雰囲気で他人を引きずって行こうとのレベルのものが多いと感じます。この意味で<解読>に難儀するゆえ、この様なレベルのエッセー或いは評論もどきが、和文英訳の問題に好んで多用されるのでは、と思います。*主張する内容は月並みで新奇性novelty は有りません。逆に言えば、その様な月並みな主張のパターンを、英文解釈であれ和文英訳であれ一定程度頭の中にインプットすれば受験はスイスイ行けそうです。塾長のコラム 2019年9月15日 『lost in translation 』https://www.kensvetblog.net/column/201909/20190915/で触れましたが、上田敏の訳詩に際しての覚悟の様な高度な技能は求められません。所詮は入試問題なのですから。実力のある方はセンスの良い受験参考書を入手して自己演習に励めば相当の実力は涵養出来ると想います。基本、勉学にはゼニを掛けずに頭そのものを使え、です。*和訳出来る箇所からさっさか直訳風に作成し、仕上がった荒削りな文章に、試験の時間配分を考えながらせっせと鉋掛けし語句の断片を糊付けする方針で行きましょうか。得点/時間のコストパーフォーマンスを考える事が入試では大切です。【和文の大意】*<芸術、芸能、科学の分野を問わず、非功利主義的に自分が興味を抱く未知の分野を究めたいとの欲求が文化を形作る。【英語化し易い和文への変換】*英語風な表現に変換すると「美術、音楽などの芸術や芸事の世界に於いて、誰もまだ到達したことのない領域を追い求めたいとの純粋な欲求がそれらの文化を支えている。実は科学者と呼ばれる一群の人々も知の世界の限界を追及することを楽しむ人々である。科学的成果を得ることだけでなく、知の限界を追い求める過程そのものが科学の文化を形作る。そこでは実用的かそうでないかは問題にならない。」【英文化の要点】おさらいとなりますが、*大意を掴んだ平易な英文をまず作り、今度は日本語の文意に正確に近づけるべく、英語の表現を練っていきます。流れとしては、①和文の修辞、日本語固有の表現をはぎ取り論理的且つ平易な文章に直す②自分の知っている平易な英語にさっとひとまず英訳(これでそこそこの配点は得られる)③和文原文のもつ意味合いに修整、推敲(時間的余裕があれば)となります。 |
||
 |
 |
Bob Dylan - Hurricane (Lyrics Video) Full Original Version
2019/07/27 Marshall's Studio https://youtu.be/b_SUNDJT9DY
LP Desire 収録。当時の米軍極東放送にて毎週土曜の午後から放送されていた All American
Top 40 ではこの曲の一部が望ましくないとしてピーと言う音で消されていました。確かに下品な
表現は含まれていますが、ディランの、英語に強弱を置く発音から大変聞き取り易く感じます。塾
長はこのLPを50回は聞いていますが、この Hurricane に登場する英語表現-極めて普通の英
語表現-が楽に理解出来るレベルであれば入試の英作文も軽く突破出来るでしょう。当英語コラ
ムを通じそれが可能になる筈です。
"To be, or not to be, that is the question" 2018/04/12 Andrew Scott, as Hamlet,
performs the opening lines of Shakespeare's most famous soliloquy. (via BBC Arts)
https://youtu.be/7iDds31CdNA
ハムレット開幕冒頭の最も有名な独白シーンです。
 |
 |
|
和文英訳の問題に接して感じますが、悉無的表現に階調 gradation を添えてまともな日本語をまずモノして欲しいと、注文したくなる様な日本語が多いですね。英文和訳の入試問題のコラムで書いたことですがこれまた見た事も無い奇矯な英文が出たりで、受験生を意図的に誤解に誘導する意地の悪さを含ませているのかと感じもします。こんな按配で塾長も入試英語に接すると正直疲れを覚えることが多いです。奇妙な出題文に対して、まず英-英変換、日-日変換に頭脳パワーを浪費させられるからです。何故低レベルの説教臭い三流評論もどきの内容を、塾長が過去30年一度も見たことも無い様な妙な文章で記述し、受験生側の迷いを生むような真似をするのかと甚だ残念に感じています。パズルを解かせる方針なのでしょうか?しかし語学がパズルであるとすれば哀しい話です。 今回採り上げた和文英訳の問題で一番伸びやかでそれでいながら受験生の英語力を問う好出題が京都大学のものと感じました。敢えて分かり難い、言語表現として稚拙な問題文を掲げる大学は、出題する英語担当教員(英文科所属?)の精神が時代錯誤的 (anachronic) なのではと塾長は率直に考えます。戦前の旧制高校での教養科目の授業が非常に優れていたと聞きますが、この様な英語の出題傾向は、その中の、排除すべき悪しき因習部分をひょっとして引きずっているものかなどと想像もしています。 この様な事を考えると、大学入試の英語科目は適宜廃止し、公平性と客観性が担保されればですが、他の英語資格の成績点数で代えるのも合理的かなと思います。 受験生の方々は入試英語とはこんなものだと割り切って入試をくぐり抜けてしまい、早く大学生になって羽ばたくのが最善です。当塾としても大学生以上の方、社会人の方に対して英語指導を行うことを旨としており、入試英語指導を直接のターゲットにはしていません。 入試の英作文は相手側が出した課題を上手く和訳する操作に過ぎず、受け身での英文作成ですが、自身がオリジナルな内容を和文で作成しそれを英語に変換しようとする過程で(勿論、最初から英語で執筆し始めるのも OK)、英語の実力が真に自分の血肉となる様に思います。自分が言いたいことが本当に英語で誤解無く十分に表現し得ているか、それが native に大きな違和感なく読んで貰える内容か、などと一語一句から推敲する必要がありますが、それを通じて力が付く訳です。最終的に rewrite を依頼する native (勿論教養水準の高い相手)との間で、本当は斯く斯く然々のことをこの点で表現したいがより適切な表現はあるかなどと遣り取りすること自体が書き言葉としての英語力を高めてくれます。 世には受験産業として医学部専門予備校などが沢山有り(学費は年間数百万はザラです)、そこでの英語担当は過去の予備校勤務にて合格実績が豊富な者がより集められているものと推測しますが、相手(大学)が出した問題を受け身的に対応し、入試動向に合わせた知識の切り売りをし、生徒の尻を叩き医学部に送り込むのが職責です。入試までの時間も限られ、また他の科目との兼ね合いもありますので、じっくり英語の本格的な指導を行いたくとも行う事は不可能です。入試動向に照準を合わせ、エッセンスを効率よく指導するのでしょうね。尤も、彼らの努力で希望する学部に押し込んで呉れ、人生への道を開いて呉れますので、明確性の低い授業をダラダラ続ける高校英語教師よりは予備校講師の方が遙かに感謝されるのは事実でしょう。但し、指導を受けて技術的に英語の得点は取れる様になり目出度く大学に入学を果たし得ても、英語に苦手意識を抱いたままの者が日本にごまんと存在するのが現実です。入試英語は一度忘れてしまい、最初から英語をじっくり学び直すべきですが、その様な場は大学にはありません。東大や医学部に入学しようが英語圏で moderate scientist と呼称される者 (教養として Nature や Science の内容が読み取れるクラス)が普通に読みこなす英語論文がスラスラ読めませんし、ましてや論文執筆など出来ません。これらは自前で経験を重ねて実力を身に付ける他はなく、例外は除き指導はされません。お困りの方は高度な教養レベルの指導者がコーチする当塾を是非活用戴ければと思います。 これまで過去5回に亘り、英訳の問題を解き明かしましたが、これらは英文を作成するに際しての推敲過程そのものを例示します。詩歌の翻訳でもありませんので常にこの様な時間を掛けての検討は不必要ですが、塾長の遣り方を参考にじっくり改訂する<入試英語後の>プロセスを一度経験しておくと良いと思います。まぁ精読ならぬ精訳ですね。この様な自分なりの思考過程を身に付けておき、将来ご自身がオリジナルな中身を持った際には、それを世界に向けて意図が正しく伝わる様に発信して下さい。必要は成功の母と言いますが、脂汗、冷や汗を流し、赤っ恥をかきながらでも確実に英語力が身に付くはずです。 全5回の 2020年入試和文英訳のコラムは今回で終わり、次回からまた、主に大学入学後の方々を対象とする英語表現のコラムに戻ります。 |
||
 |
 |