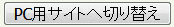英文読解から入試まで 完全マンツーマン指導
https://dictionary.cambridge.org/ja/dictionary/english/
塾長のコラム 2025年6月1日
 |
 |
|
分詞構文1 |
||
2025年6月1日 皆様、KVC Tokyo 英語塾 塾長 藤野 健です。 これまでのシリーズの中にてところどころ断片的に分詞構文についての説明を行って来てはいましたが、意外や纏めて解説した事は無く、本構文シリーズの1つに加えるのも悪くない、いや欠かす方が寧ろおかしいぐらいですね。学校英語の場でも入試に際しても、必ず解釈を問われるのが分詞構文ですので、その意味合い並びに成立をがっちりと把握しておくことは勿論大きな強み、得点源となります。長文読解などに於いて、文構造が把握出来ない、何を言っているのか不明で困る、などのシーンでは、分詞構文が使用されているかどうかをまず見抜くことがキモになりますし、その様な<ヒネた>文章ゆえ、-誰でも分かる英文を和訳させても点差が付かなくなる-和訳しなさいなどと設問が為されることになります。特に難関大学の入試では、with で始まる付帯状況を表す分詞構文の意味をどうやって日本語に好適に変換するのか、などに習熟しておく必要があるでしょう。この辺りは、扱い方、和訳の遣り方の型がありますので、知っておいて損な事は全くありません。余談ですが、これまで扱って来た、条件法、否定、比較、倒置、省略、挿入、強調表現などに加え、分詞構文、更には関係詞も我が懐中の物としておく- native の規定する英語習熟度のランキングで言うと C1 advanced level 以上に相当します-と、語彙の面は別として、大学入試のみならず英語圏での文章にはほぼ対応が出来ることになります。逆に言えば、英文読解の極意ここにあり、なのですが、英語とは或る意味単純明快な言語であるとも言えましょう。 いわゆる付帯状況や情報の追加説明を便利に表現出来る用法を除き、口語では利用されることは普通は見られませんが、基本的に non-fiction writing ではなく、fiction writing に利用される表現として、分詞構文は軽い記述の書き物、エッセイ、に始まり、重々しい文学作品に至るまでの幅広い範囲で頻用されます。non-fiction に於いては、例えば(少なくとも現行の)自然科学の学術雑誌では、編集部の方針で利用を禁じていることが殆どですし、分詞構文の或る特定の記述形式(文末に、カンマ+doing の形で文を延長する単純接続の分詞構文)のみOKを出す雑誌も存在します。何故かと言うと、本来的に明確な意味を持つ接続詞を用いて文を明確に記述すべきところ、論理結合子である肝心の接続詞、更には主語までを省略し、副詞句として主文に添える形が分詞構文だからです。詰まりは、文が簡潔になったのは良いが、意味合いに曖昧性を持ち込んでしまう大きな欠点を併せ持つのが分詞構文になります。別な見方をすれば、書き手側が本来的にどの接続詞を用いるべきかを意識することなく、<取り敢えず知的にも見えるしサラっとこの修辞法を用いて文を述べて繋いでしまおう>との意識の表れか、とも言えそうです。これでは、読者に対して揺るぎの無い明確性に立ち真実を伝えんとする学術論文の場では適当な表現法とは言えなくなるのは自明かと思います。言わば、口語では利用されず、文章中では formal などとされて頻用されるものの、厳密な意味合いを伝達する場では利用出来ない、との半端な性質を持つ表現になります。まぁ、文学的な修辞に近い立ち位置ですね-表現に曖昧性を含ませることが(少なくとも嘗ての)英語の文学性の1つの特徴だったのかと勘ぐりたくもなります・・・。この様な分詞構文の抱えるマイナス点を明確に説明する国内外の動画などは塾長は殆ど見たことがなく、鹿爪顔で分詞構文の一通りの説明を事務仕事のように加えて済ますだけで、分詞構文利用の実態やその精神にまで深く踏み込んだ例は数少ないです。塾長は理系研究者としての経験と立場から、この様な点に対しても第三者的な切り込みを入れつつそろりと、いや濃厚に!、説明を加えて行きます。本シリーズの第1回目です。 British Council Learn English Grammar C1 grammar Participle clauseshttps://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/c1-grammar/participle-clauses『試験に出る英文法』 森一郎、青春出版社、1971年 第3章現在分詞・過去分詞 pp.48-53『チャート式 英文解釈』 鈴木進、数研出版、昭和51年、<第2編文の構造上よりの解釈 第2章句を中心として>ここの基本的構成並びに(難解な)例文を幾つか参考にしていますが、塾長なりの視点から批判的検討を加え、また一部、より現代的な、或いはより正しい明確な表現となる様、書き換えたものも併記しています。 |
||
 |
 |
ALL Grammar for ADVANCED (C1 Level) English in 12 minutes in 2025
English with Lucy 2025/01/10 https://youtu.be/w7ZZdVlpOeo
C1 advanced level の者が履修を済ませておくべき文法事項が紹介されます。
一点の曇り無くこれらを理解出来て居れば本邦の大学入試程度は勿論の事、
海外にて通常の社会生活を営む上で大方の英語に対応可能になります。
4:00からチラと分詞構文の解説が始まります。
Participles MrKeller 2020/03/24
https://youtu.be/Y3jeDj9eeL8
6:30 から分詞構文についての丁寧で分かり易い説明が始まります。
印字した用紙 を用いて素朴に説明を加えていく手法には、各種の編集を加えた
最近の動画に比して中身の質に於いて何ら遜色なく、優れた方法と感心しました。
塾長もこの遣り方を参考にしてサッと動画を作れたらと考えて居ます。
 |
 |
|
分詞構文 Participle construction とは何か?分詞とは何ですか?*<分詞>とは、動詞から分かれ出た語、の意味になります。*英語では、分詞は現在分詞と過去分詞の2つに限定されますが、言語に拠っては(例:ラテン語)未来分詞なるものを持つものもあります。*本来的に、<各時制に応じて使い分けるべく動詞から派生した形式>、が分詞ですね。*基本的に形容詞や副詞として働くと考えれば良いでしょう。*各種の分詞使用用法の内の、固有の様式を持つ副詞として機能する文章形式を分詞構文と呼称し、分類・整理が行われている話になります。分詞構文の定義*<分詞を利用した構文>には、分詞を文全体や動詞を修飾する副詞句として利用するものや主文に対して情報を追加・記述するもの(以上、本シリーズでの<分詞構文>)、並びに、分詞を名詞を修飾する形容詞として利用するものがあります。*<分詞構文>にも様々なものが含まれますが、それらの各定義に関しては、文法的な規準と意味用法に基づく規準の綯い交ぜになったものが大半であり、各解説者により揺らいでいるのが実情に見えます。*複層的な分詞構文成立の歴史的背景もあり、一筋縄では定義はすんなりとは進まないことをまずはご理解下さい。*本シリーズに於いては塾長は<分詞構文>を以下の様に2つ-基本的に複文と重文のいずれに相当するのか-に分けて定義し、解説を進めていきます:*複文(従属接続詞で繋がれる文)にせよ、重文(等位接続詞で繋がれる文)にせよ、片方の文の動詞を分詞化して繋いでしまえば分詞構文化出来るとの一種の安易性もあり、元の文が複文相当なのか、重文相当なのか明確な区分けを行い切れないところも存在します。*以下の分類-本シリーズで塾長が次回以降展開するもの-にしても、きっちりした線引きが出来ないもの、いずれにも該当するもの、もそこそこ存在する事を十分にお含み置き下さい。*まぁ、大まかな1つの分類方法になります。*意味用法からの分類:分詞構文=A+BA.(狭義の)分詞構文 (分詞利用表現+主文の順序となるものが多い、時、付帯状況、理由、譲歩、条件を表す従属接続詞を失った複文): 副詞句を形成B.疑似分詞構文 (主文+分詞利用表現の順序となるものが殆ど、広義の情報追加を表す構文: 等位接続詞 and を失った重文)= 結果の分詞構文( 主に and で接続可能) + 情報追加の分詞構文(関係代名詞 which の非限定用法などを利用して置き換え可能)*付帯状況は厳密には主語の同時的性状(動作、状態)を付加的に追加説明する用法ゆえ、これは従属接続詞 while (~しつつ)或いは with などを用いて書き換える事も可能ですが、主文の後に付加的な説明を分詞(現在分詞、過去分詞)、或いは形容詞などを用いて文を続ける用法も頻用され、これらは等位接続詞を用いての書き換えも可能な場合があります。*主文の後ろに分詞を添えるものは、そして~する、との時間差をも表し得、これは厳密には完全な同時性を表すべき付帯状況の用法とは言い切れませんが、同時性の幅を拡大して考えれば付帯状況と捉えることも可能です。*実際のところ、主文の後に付加的な説明を分詞や形容詞などを添えて用いる用法は日常的に(軽い書き物などでも)頻用され、「while を用いて書き換えられる場合は、副詞的用法だから狭義の分詞構文だ、and を利用して書き換えられるから疑似分詞構文だ」などと、native は全く区別する事も無く、主文の後ろに追加の文言をズラズラ(或いはダラダラと!)加えて行きます。*従って、主文の後ろに追加的情報を加える用法は総じて上記A (~しつつ)かB(そして~)かの区別が付きにくくなる場合があります。*まぁ、広義の付帯状況を表す分詞利用構文だ、と考えるのも合理性を持ちますね。*構造からの分類: 主文と分詞の主語の一致、違いに基づく分類(狭義の)分詞構文: 主語の一致する分詞構文+独立分詞構文+無人称独立分詞構文+前置詞独立分詞構文疑似分詞構文: 主語の一致する分詞構文+独立分詞構文+前文内容を主語とする分詞構文-----------------------------A.(狭義の)分詞構文とは何ですか*話し手、書き手の頭の中には、<従属節(副詞として主文全体に掛かる)+主節>が一度或る程度はその形を成立させており、次いで、この内の従属節を節(SV構造を持つもの、要するに文)の形を失わせ、接続詞、更には主語を削除し、動詞を分詞に転じ、句に縮小した上で利用する、 economic (言葉の節約)の為の修飾構造を(狭義の)分詞構文と呼称します。*この省略、変形の過程で従属節内に存在していた絶対的な時制を失い、主文に対しての相対的な時制表現しか持たなくなります。*短く出来る分だけ、キビキビとした記述にも出来ますが、ヘタをすると意味が不鮮明になる危険性も持ち合わせて居ます。+実際のところ、書き手側の頭の中で、明確な接続詞(時、同時進行、理由、譲歩、条件などの従属接続詞)を思い浮かべるまでもなく、取り敢えず言葉に出して仕舞おうとの精神状態の上に、分詞構文を仕立ててしまうケースも完全に無いとは言い切れないでしょう。*まぁ、基本は分詞利用表現側は副詞句-主文に対する添え(=副え)物-ですので、軽く扱われるという話です。*時、同時進行、理由、譲歩、条件などの副詞的意味用法で利用されます。*分詞利用表現+主文、の順序で利用されるケースが大半です。*尤も、理由を表す分詞利用表現は、文中、文末に置かれる場合も見られます。*手抜きの修辞表現なのか、気取った formal 表現なのか、と判断は迷いますが、この意味自体に於いても非常に文学的な表現用法と言えるでしょう。*書き手側の文意を正しく判断してくれるかは、前後の文脈、読み手側の判断力-いわゆる常識-に左右されます。*日本語の古文の時間で、この文は一体何を語っているのか皆目見当がつかない、遣ってられない!、と感じた方は多々おられるかと思いますが(理系アタマの塾長も当時は苦しみました!)、それと同様、意味の取りにくい分詞構文にて文をモノすると、その分だけ読者は確実に逃げて行きます。*簡潔、明快な意思表示が望まれる現今に於いては、基本的に歓迎されなくなりつつある修辞法と言えそうです。*元々短くて意味の分かりやすい従属節を分詞表現化することにより、更に端整で短い文言で表現することが出来ます。*問題は長々とした従属節を分詞化する際に発生し、文の意味が取りにくくなりますし、読み手側に余計な負担を掛けることになります。*接続詞と主語が省略出来るだけですので、長い従属節ほど分詞化してeconomic に出来る割合は低下してしまい、逆に意味が取りにくくなるデメリットが急激に高まります。*斯くして、特に自然科学系の学術論文に於いては、<使わないで貰えますか?>と編集側から求められることになります。*省略される従属接続詞は、時間の接続詞 (after, before, while, when など)、並びに理由の接続詞 (because, as, since) が殆どを占めます。*条件の接続詞 if や、譲歩の接続詞 though が略される場合は定型的な表現にほぼ限定されてしまい、利用されるケースは少ないです。*これらの従属接続詞は、文意を明確にするために、省略されずに残す例もしばしば観察されます。しかしこれだと文を縮めるメリットも幾らかは失われます。*主文と分詞構利用表現との間に時制の差がある時は、古い方(分詞構文側)を完了形で記述します。*現在完了(これは時制上は現在形)+現在形の場合も、分詞構文側は完了分詞になります。*これを<元に戻す>場合、過去+現在、なのか、現在完了+現在なのか区別出来ません。*文脈から判断するしか有りませんが、曖昧性が排除出来ませんね。*分詞利用表現中の being, having been は通常は省略されます。*分詞の前に not を付けると意味を否定化出来ます。*doing to do を否定にする場合は not doing to do, doing not to do のいずれでもOKですがニュアンスは変わります。*従属節側は原理的には全て分詞化することは可能ですが、分詞化するしないのどこに線引きをするかは程度問題ということになります。*文構造としてのバランス、語呂合いの問題も出て来ますし、書き手側の文学的な美意識なども大きく反映されるでしょうね。*分詞の主語と主文の主語が異なる場合は、分詞側の主語は省略しません(独立分詞構文と呼称します)。*意味用法的には主語を略すものと基本的に同じです。 |
||
 |
 |
【実は使える】分詞構文をマスターできればスマートに見えます。〔#53〕
StudyIn ネイティブ英会話 2020/11/2 https://youtu.be/cf2hvuw1wJ4
6分以降に、分詞構文はどの様な場でどの様な意識で利用されるのかの
肝心要の説明が為されます。これは大変貴重な情報です。意味を教える事
も大切ですが、それ以上に<この英語はどの様なシーンで用いられるのか>、
その肝心なところが従来の日本の英語教育ではしばしば欠落していました。
formal vs. informal の視点、その程度具合の欠如です。
 |
 |
|
B.疑似分詞構文とは何ですか*主文の文末に、<, doing >の形で次を続けるものの、主文とその句の間に主従の関係が成立せずに時間差を伴う do A and/but do B の意味関係を示す(次の動作を示す、或いは結果を意味する)構文、また、前文或いはこれの一部構成要素に対する追加的説明(非制限用法の関係代名詞 which などを用いて書き換え可能)をす加える分詞利用の構文が存在します。*端的に言えば、全て新たな情報、思考を追加する用法です。*時、同時性、理由、譲歩、条件などの副詞的意味用法は持ちません。*ここでは、その類いの構文を疑似分詞構文と呼称することにします。*分詞の主語と主文の主語が異なる場合は、分詞側の主語は省略しません(独立分詞構文と呼称します)。*意味用法的には主語を略すものと基本的に同じです。*主文+分詞利用表現、の順序で基本的に利用されます。*従って、この用法は副詞句作成に相当せず、主語に続く文の等位接続詞と主語を省き、動詞を分詞化して繋いだだけ、或いは、関係代名詞を使わずに分詞を用いて文を続ける用法であり、分詞利用構文には違いがありませんが、上記Aタイプの分詞構文(狭義の分詞構文)とは言えません。*当然乍ら、主文の前に分詞表現を付け加える事は出来ません。後ろのみです。*学参(=学習参考書)などに拠っては、分詞構文とは分詞側が副詞句を構成するものであると定義を掲げておきながら、この用法を、<分詞構文の動作連続用法であり、and で繋げられる>などと、首尾一貫しない、矛盾した説明を加えて茶を濁すものもあります。*この辺りは、分詞構文に対する明確な分析を述べずに<分詞を使った文章表現 participle clauses / participle sentenses>の中に押し込んで説明を加える native 等も多いですね。*しかし、文法的な説明が曖昧性を排除出来ずに説明者側が各自各様ではあるにしても、実は初学者にはこの程度の解説で全く不足はしません。*塾長はこちらのタイプを<疑似分詞構文>と呼称しますが、便宜的に<結果の分詞構文>、<情報追加の分詞構文>と呼ぶのも良いでしょう。*疑似分詞構文は、意味の曖昧性もだいぶ排除されますので、一部の学術論文などでは使用が認められている場合もあります。*分詞を利用した構文ゆえ、広義の分詞構文にはなりますね。*<, doing >の意味上の主語は、主文の主語に一致する単純明快な場合もありますが、主文全体、或いはその一部となることもあります。*まぁ、2通りある訳ですが、その内の後者の方-which を用いて書き換え可能-は そこそこ頻用されますが一種の特殊用法と言えます。*疑似分詞構文に於いて、別の主語を添えて<独立分詞構文>化させているものもありますが、そこに狭義の分詞構文としての機能は無く、<情報追加の分詞構文>、<結果の分詞構文>のいずれかであることには違いは有りません。*独立分詞構文とは、動作主体が異なる場合にそれを主語として添えるだけの違いに過ぎません。 |
||
 |
 |