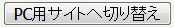英文読解から入試まで 完全マンツーマン指導
https://dictionary.cambridge.org/ja/dictionary/english/
塾長のコラム 2025年6月15日
 |
 |
|
分詞構文4 |
||
2025年6月15日 皆様、KVC Tokyo 英語塾 塾長 藤野 健です。 これまでのシリーズの中にてところどころ断片的に分詞構文についての説明を行って来てはいましたが、意外や纏めて解説した事は無く、本構文シリーズの1つに加えるのも悪くない、いや欠かす方が寧ろおかしいぐらいですね。学校英語の場でも入試に際しても、必ず解釈を問われるのが分詞構文ですので、その意味合い並びに成立をがっちりと把握しておくことは勿論大きな強み、得点源となります。長文読解などに於いて、文構造が把握出来ない、何を言っているのか不明で困る、などのシーンでは、分詞構文が使用されているかどうかをまず見抜くことがキモになりますし、その様な<ヒネた>文章ゆえ、-誰でも分かる英文を和訳させても点差が付かなくなる-和訳しなさいなどと設問が為されることになります。特に難関大学の入試では、with で始まる付帯状況を表す分詞構文の意味をどうやって日本語に好適に変換するのか、などに習熟しておく必要があるでしょう。この辺りは、扱い方、和訳の遣り方の型がありますので、知っておいて損な事は全くありません。余談ですが、これまで扱って来た、条件法、否定、比較、倒置、省略、挿入、強調表現などに加え、分詞構文、更には関係詞も我が懐中の物としておく- native の規定する英語習熟度のランキングで言うと C1 nadvanced level 以上に相当します-と、語彙の面は別として、大学入試のみならず英語圏での文章にはほぼ対応が出来ることになります。逆に言えば、英文読解の極意ここにあり、なのですが、英語とは或る意味単純明快な言語であるとも言えましょう。 いわゆる付帯状況や情報の追加説明を便利に表現出来る用法を除き、口語では利用されることは普通は見られませんが、基本的に non-fiction writing ではなく、fiction writing に利用される表現として、分詞構文は軽い記述の書き物、エッセイ、に始まり、重々しい文学作品に至るまでの幅広い範囲で頻用されます。non-fiction に於いては、例えば(少なくとも現行の)自然科学の学術雑誌では、編集部の方針で利用を禁じていることが殆どですし、分詞構文の或る特定の記述形式(文末に、カンマ+doing の形で文を延長する単純接続の分詞構文)のみOKを出す雑誌も存在します。何故かと言うと、本来的に明確な意味を持つ接続詞を用いて文を明確に記述すべきところ、論理結合子である肝心の接続詞、更には主語までを省略し、副詞句として主文に添える形が分詞構文だからです。詰まりは、文が簡潔になったのは良いが、意味合いに曖昧性を持ち込んでしまう大きな欠点を併せ持つのが分詞構文になります。別な見方をすれば、書き手側が本来的にどの接続詞を用いるべきかを意識することなく、<取り敢えず知的にも見えるしサラっとこの修辞法を用いて文を述べて繋いでしまおう>との意識の表れか、とも言えそうです。これでは、読者に対して揺るぎの無い明確性に立ち真実を伝えんとする学術論文の場では適当な表現法とは言えなくなるのは自明かと思います。言わば、口語では利用されず、文章中では formal などとされて頻用されるものの、厳密な意味合いを伝達する場では利用出来ない、との半端な性質を持つ表現になります。まぁ、文学的な修辞に近い立ち位置ですね-表現に曖昧性を含ませることが(少なくとも嘗ての)英語の文学性の1つの特徴だったのかと勘ぐりたくもなります・・・。この様な分詞構文の抱えるマイナス点を明確に説明する国内外の動画などは塾長は殆ど見たことがなく、鹿爪顔で分詞構文の一通りの説明を事務仕事のように加えて済ますだけで、分詞構文利用の実態やその精神にまで深く踏み込んだ例は数少ないです。塾長は理系研究者としての経験と立場から、この様な点に対しても第三者的な切り込みを入れつつそろりと、いや濃厚に!、説明を加えて行きます。本シリーズの第4回目です。 British Council Learn English Grammar C1 grammar Participle clauseshttps://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/c1-grammar/participle-clauseshttps://www.ldoceonline.com/jp/dictionary/think-to-do-something『試験に出る英文法』 森一郎、青春出版社、1971年 第3章現在分詞・過去分詞 pp.48-53『チャート式 英文解釈』 鈴木進、数研出版、昭和51年、第2編文の構造上よりの解釈 第2章 句を中心としてここの基本的構成並びに(難解な)例文を幾つか参考にしていますが、塾長なりの視点から批判的検討を加え、また一部、より現代的な、或いはより正しい明確な表現となる様、書き換えたものも併記しています。https://ypir.lib.yamaguchi-u.ac.jp/bg/215/files/135479現代英語の分詞構文(その1) 一Anima1 Earmの分詞構文一福島一人 英米文学研究 20 巻 141-170 頁 1984-12 発行紀要論文 出版者 梅光女学院大学英米文学会[ISSN] 0288-0075*分詞構文の使用頻度の高い George Orwell, Animal Farm を素材として、全158用例についての分析を行って居ます。野口正樹 『分詞構文の心 ― Pedagogical Grammar ― を基盤にして』沖縄国際大学外国語研究, 巻 21, 号 2, p. 38-56, 発行日 2018-03https://okiu1972.repo.nii.ac.jp/records/532https://okiu1972.repo.nii.ac.jp/record/532/files/1343070x_21_2_NoguchiMasaki.pdfhttps://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/withhttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/withSTUDYFileshttps://studfile.net/preview/4511119/page:58/*ウクライナの英文法解説サイトです。*Advanced Grammar in Use Martin Hewings, CambridgeUniversity Press などよりは詳しい内容に見えます。紀要論文、<言語篇>日本語研究における「付帯状況」の導入を辿る試み菊池 そのみ文藝言語研究 巻 82, p. 41-63, 発行日 2022-10-31https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/records/2005219https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/record/2005219/files/SLL_82-41.pdf |
||
 |
 |
Participle clauses - English grammar lesson
Crown Academy of English 2023/11/14
https://youtu.be/b1jdmm4gpHk
最初に登場する例文では従属接続詞にwhile が用いられていますが
これを省けば、同時進行を表す分詞構文、即ち付帯状況を表す分詞
構文の1つが成立します。
 |
 |
|
A.従属接続詞の意味を含み、主文に対する副詞句として機能する分詞構文2 (つづき)5.動作・状態の同時性(=付帯状況)を表す分詞構文*これは、付帯状況を表す分詞構文として一般的に呼称されます。*2つの事象が<キッカリ>同時に併行して起きている事を表す分詞構文です。*時を表す分詞構文の一種と言えます。更にそれが時間的に鋭くピンポイントになった形ですね。*<~しつつ、~しながら、~されながら、~の有様で>、の意味で、主文に掛かる副詞句として機能します。*付帯状況なる引っくるめた言葉で一般的には呼称されますが、同時動作を表す場合には<状況>の語は合いませんね。*完全文の後ろに、分詞、形容詞或いは with +名詞(+形容詞)などを添えて付帯動作・状況を示す<気軽な>用法が英語には元々存在しますが、その内の分詞利用のものを<付帯状況を表す分詞構文>と採りあげて呼称出来ますし、主文の前に置いて利用する場合もあります。*~しつつ、の文言ですので、基本的に主文の前後いずれに置く事が出来る訳です。*この様な付帯動作・状況の分詞構文を通常の文、即ち節形式で表すのは難しいとされています。*これに変わる簡便な記述法が無いこともあり、口語でも頻用されます。*野口正樹氏によれば、「(付帯状況の分詞構文は)日常会話のみならず書き言葉でも重宝される用法である。主語が先にあるので,この用法は追加説明に好都合である。分詞構文の 80%以上がこの付帯状況の用法である。}とされます。野口正樹 『分詞構文の心 ― Pedagogical Grammar ― を基盤にして』 p.44沖縄国際大学外国語研究, 巻 21, 号 2, p. 38-56, 発行日 2018-03 https://okiu1972.repo.nii.ac.jp/records/532*口語やcasual な表現の場では主文の後ろに分詞を添える形式にほぼ限定されます。*これを<無理遣り>節に変換する際には、[同時進行を表す接続詞 while (at the same time that, simultaneously) +進行形・状態の記述] なども利用出来ます。*あっさりと2文に切り離す手も利用出来ますが、読み手に対して、「君たち、同時性である事を文脈から読み取って呉れ、頼む!」、の姿勢です。*記述そのままに付帯的状況、動作だと理解するのが実は最善と言う訳です。*人物や事象の状況説明を加える場合に頻用されますが、実際のところ、<, doing >の形式の場合、同時なのか、and do の意味なのかの曖昧性を持ち、同時であれば副詞的用法~しつつとし、and を使って解釈出来れば、副詞的用法ではなく、次の動作情報を加える用法、即ち疑似分詞構文だ、と文法的には区別は可能ですが、native はそんな事にはお構い無しに、特に区別なく、主文の(おおかた)後ろに、分詞でズラズラと!文を続けるのが実際のところです。*文脈に拠っては、時間、理由、譲歩、条件のようなニュアンスで解釈可能な場合もあります。*まぁ、意味合いの曖昧性は免れません。Waiting for Ellie, I made some tea.→While I was waiting for Ellie, I made some tea.エリーを待ちながら、私はお茶を入れた。= I made some tea waiting for Ellie,They were watching TV (while) listening to music.音楽を聴きながら彼らはテレビを見ていた。→They were watching TV while they were listening to music.While looking for my key, I happened to find the book I hadlost.鍵を探してたら、前に失くした本をたまたま見つけたんだよ。→While I was looking for my key, I happened to find the book I had lost.The Piper went up the mountain, followed by the dancingchildren.パイパー(笛吹き)は山を登り、踊る子供たちが彼の後ろに続いた。(followed の前の being が省略されています)→The Piper went up the mountain while the dancing children were following him.踊っている子供たちが後を追う中、パイパー(笛吹き)は山を登っていった。= The Piper went up the mountain, and he was followed by the dancing children.(これで同時進行の意味にも取れますが、and 以下が真に同時だったのかについては曖昧性が残ります。)In sheer malignity,thinking to set back our plans and avenge himself for his ignominious expulsion, this traitor has crept here.(George Orwell, Animal Farm Chapter 6 から)まさに悪意を持ち、我々の計画を頓挫させ不名誉な追放の恨みを晴らそうと考えながら、この裏切り者は、ここに忍び込んできた。→In sheer malignity,with the thought of setting back our plans and avenging himself for his ignominious expulsion, this traitor has crept here.*分詞構文のままの方がスッキリした記述で好適に見えます。*think to do = try/plan/intend to do ですが、Collins や Cambridge 英英辞典にこの用法の記述がありません。*Longman にのみ、文語用法との記述がありました。確かにこの用法は目にしません。*ほぼ死語と言えるでしょう。*以前に、さる著名な米国憲法学者の論文中に、understand something to beの用例を見たことがあるのですが、Collins や Cambridge 英英辞典ににこの用法の記載はありません。尤も、Longman には記載がありました。*死語になりつつあるのか、新たに出現した casual 表現か、方言なのか、は不明ですが、一般的用法では無いのは確かでしょう。*意味はしっかり通じます:<~であると理解している> |
||
 |
 |
A Kind Waitress Paid for an Old Man’s Coffee Never Knowing He Was aBillionaire Looking
Soul-Stirring Stories
https://youtu.be/xn6ldU5CrsQ
同時動作・付帯状況を表す分詞表現-通常の分詞構文、独立分詞構文、前置詞独立
分詞構文-が多用されますが、それが小気味良い英語固有のリズム感を産み出して
朗読されるのが感じ取れるでしょう。取り敢えずは最初の10分程度を丹念にヒアリング
して下さい。英文としては標準的な難易度に見えます。
・・・但し正直なところ、塾長には分詞表現の使い過ぎにも感じますね。
 |
 |
|
Prepositional absolute construction前置詞独立構文*前置詞 with には、~を伴って、或いは、~を利用して、などの非常に多くの意味用法があります。*その中に、< with +名詞+前置詞句等>を副詞句として利用し、付帯状況を表す表現が存在します。*これは、with を用いて、人や物が何かをするときの位置や様子、状態を述べる際に使う用法です。*まぁ、身体や物体の状態を表す用法になりますが、分詞を使わない付帯状況に相当します。*名詞と前置詞句等の関係が、S,V関係になっていることにご留意下さい。*即ち、分詞を利用していないと言うよりは、間の being が省略されていると考えるべき形式になります。**しかも、この名詞は主文の名詞とは別のもの、即ち、独立absolute しています。*これを、ちょっと大げさに感じるかも知れませんが、前置詞独立構文 prepositional absolute construction とも呼称します。*この用法に、更に分詞を加えて< with +名詞+分詞+前置詞句>とすれば、付帯状況を表す立派な分詞構文、即ち、前置詞独立分詞構文 Prepositional absolute participle construction が成立することになります。*前置詞独立分詞構文に関しては、独立分詞構文についての解説を途中に挟む関係から、一旦間を置いて離れてしまいますが、本シリーズの最後の方(塾長のコラム 2025年7月15日)にて解説致します。Joanne stood with her hands on the sink, staring out the window.ジョアンは流しに手をついて立ち、窓の外を見つめていた。= Joanne stood staring out the window.with her hands (being) on the sink.(ここの stood は、link verb 即ち 一種の be 動詞 として機能しています)He stood there with his hands in his pockets.彼は両手をポケットに入れてそこに立っていた。Michelle had fallen asleep with her head against his shoulder.ミシェルは彼の肩に頭を預けて眠っていた。He left home with the lights on.彼は電気をつけたまま家を出た。(この on は副詞です)以下幾つかの例文は、下記サイトからお借りしています:https://studfile.net/preview/4511119/page:58/I found him ready, and waiting for me, with his stick in his hand.彼は準備万端、ステッキを手に私を待っていた。It was with an enormous feeling of relief that Lucia watched Rubio return with a wrapped cross under his arm.ルシアは大きな安堵感とともに、腕の下に十字架を巻いたルビオが戻ってくるのを見た。Sikes, with Oliver’s hand still in his, softly approached the low porch, and raised the latch.サイクスはオリバーの手を握ったまま、そっと低いポーチに近づき、掛け金を上げた。日本語に於ける付帯状況*付帯状況なる用語は皆さんも良く耳にされると思いますが、英文法用語としてこの意味の文言が英語圏に存在するのかと検索を掛けても全く見付かりません。*日本語の付帯状況の語にて例えば youtube 動画を検索すると、日本人の、如何にもサラリーマン風の予備校教師らの紋切り型の解説がズラッと現れるのが半ば滑稽に不思議にも感じるのですが、<付帯状況>なる語が、<日本人に拠る英文法解説>の場で奇妙にも跋扈している要にも思えます。*菊池そのみ氏は 『<言語篇>日本語研究における「付帯状況」の導入を辿る試み』 にて、日本語文法の場に<付帯状況>なる用語を導入・考察した初期のものとして、1982, 1983 年の論文を採りあげています。(以下引用)「遠藤(1982)は接続助詞「て」によって繋がれた前件と後件との関係(意味用法)を整理した研究である。遠藤(1982)は接続助詞「て」の前件と後件との意味関係を(2)のように分類しており、「継起関係の派生形」(遠藤 1982:59)として D’ に〈付帯状況〉を掲げている。(2) A 前件が後件の手段・方法を表わす。B 前件が後件の様態を表わす。C 前件が後件と同時に進行することを表わす。D 後件が前件に続いて起こることを表わす(継起関係)。D’ 後件が前件とほぼ同時に起こることを表わす(付帯状況)。E 前件を原因・理由とする結果を後件が表わす(因果関係)。E’ 前件に対する評価等を後件が表わす。E’’ 通常の因果関係に反することを後件が表わす(逆接)。F 前件に対する並列・累加を後件が表わす。G 前件に対する並列・対比を後件が表わす。H 文脈依存度が高く意味を特定できないもの。(遠藤 1982: 53)]cf. 遠藤裕子(1982)「接続助詞「て」の用法と意味」『音声・言語の研究』(2),pp.51- 63,東京外国語大学音声学研究室.*これを見ると、日本語の接続助詞 [て」 が、英語の分詞構文と類似の様々の意味合いを持っており、その意味用法の中に、付帯状況、即ち同時性を表すものが含まれることに、改めて興味を覚えます。*皆様も同じ感想かと思いますが、引用されている遠藤氏の「て」に関する分類が、英語の分詞構文の意味用法の分類からの類推を得て形作られたのではないかと塾長はふと感じました。*意味が語感として明確に絞れ込めない用語、<付帯状況>を使用するのは止めて、「同時性」に置き換えるのも良い様に感じますね。*明治時代の1人2人がこの種の英文法用語を苦肉の策として日本語に置換したのだろうと塾長は想像しますが、あまり知恵やセンスがある用語とも感じません。日本語の英文法用語の奇怪さについてはこれまで散々触れて来ましたが、それを改めて覚えます。*競争原理が働かない中での翻訳、或いは命名行為は後世に禍根を残しますが、後の者らが遠慮なく改訂していけばそれで済むはずですが、英語でメシを喰っている大学人らは一体何を遣ってるんでしょう?、と理系研究者の塾長は敢えて言います。*英語の分詞構文の多重的、多義的な意味合い、またその歴史性に比肩する様な日本語表現も存在することになりますが、英語では構文としての形として存在する一方、日本語ではそれが助詞に拠り表されるとの違いが面白いですね。*塾長が、漢文の~シテ、而して、を用いて英語分詞構文の訳を当てて逃げろ!、と前に口走りましたが、似た様な事を考えついている研究者が今から40年以上前に居たことになりますね。*漢文の~シテ、而して、に関する考察-これも中国語の助字ゆえ日本語の助詞に非常に類似する存在ですね-が抜け落ちているのが片手落ちの論文だと塾長は強く感じるのですが。 |
||
 |
 |