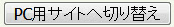英文読解から入試まで 完全マンツーマン指導
https://dictionary.cambridge.org/ja/dictionary/english/
塾長のコラム 2025年6月20日
 |
 |
|
分詞構文5 |
||
2025年6月20日 皆様、KVC Tokyo 英語塾 塾長 藤野 健です。 これまでのシリーズの中にてところどころ断片的に分詞構文についての説明を行って来てはいましたが、意外や纏めて解説した事は無く、本構文シリーズの1つに加えるのも悪くない、いや欠かす方が寧ろおかしいぐらいですね。学校英語の場でも入試に際しても、必ず解釈を問われるのが分詞構文ですので、その意味合い並びに成立をがっちりと把握しておくことは勿論大きな強み、得点源となります。長文読解などに於いて、文構造が把握出来ない、何を言っているのか不明で困る、などのシーンでは、分詞構文が使用されているかどうかをまず見抜くことがキモになりますし、その様な<ヒネた>文章ゆえ、-誰でも分かる英文を和訳させても点差が付かなくなる-和訳しなさいなどと設問が為されることになります。特に難関大学の入試では、with で始まる付帯状況を表す分詞構文の意味をどうやって日本語に好適に変換するのか、などに習熟しておく必要があるでしょう。この辺りは、扱い方、和訳の遣り方の型がありますので、知っておいて損な事は全くありません。余談ですが、これまで扱って来た、条件法、否定、比較、倒置、省略、挿入、強調表現などに加え、分詞構文、更には関係詞も我が懐中の物としておく- native の規定する英語習熟度のランキングで言うと C1 advanced level 以上に相当します-と、語彙の面は別として、大学入試のみならず英語圏での文章にはほぼ対応が出来ることになります。逆に言えば、英文読解の極意ここにあり、なのですが、英語とは或る意味単純明快な言語であるとも言えましょう。 いわゆる付帯状況や情報の追加説明を便利に表現出来る用法を除き、口語では利用されることは普通は見られませんが、基本的に non-fiction writing ではなく、fiction writing に利用される表現として、分詞構文は軽い記述の書き物、エッセイ、に始まり、重々しい文学作品に至るまでの幅広い範囲で頻用されます。non-fiction に於いては、例えば(少なくとも現行の)自然科学の学術雑誌では、編集部の方針で利用を禁じていることが殆どですし、分詞構文の或る特定の記述形式(文末に、カンマ+doing の形で文を延長する単純接続の分詞構文)のみOKを出す雑誌も存在します。何故かと言うと、本来的に明確な意味を持つ接続詞を用いて文を明確に記述すべきところ、論理結合子である肝心の接続詞、更には主語までを省略し、副詞句として主文に添える形が分詞構文だからです。詰まりは、文が簡潔になったのは良いが、意味合いに曖昧性を持ち込んでしまう大きな欠点を併せ持つのが分詞構文になります。別な見方をすれば、書き手側が本来的にどの接続詞を用いるべきかを意識することなく、<取り敢えず知的にも見えるしサラっとこの修辞法を用いて文を述べて繋いでしまおう>との意識の表れか、とも言えそうです。これでは、読者に対して揺るぎの無い明確性に立ち真実を伝えんとする学術論文の場では適当な表現法とは言えなくなるのは自明かと思います。言わば、口語では利用されず、文章中では formal などとされて頻用されるものの、厳密な意味合いを伝達する場では利用出来ない、との半端な性質を持つ表現になります。まぁ、文学的な修辞に近い立ち位置ですね-表現に曖昧性を含ませることが(少なくとも嘗ての)英語の文学性の1つの特徴だったのかと勘ぐりたくもなります・・・。この様な分詞構文の抱えるマイナス点を明確に説明する国内外の動画などは塾長は殆ど見たことがなく、鹿爪顔で分詞構文の一通りの説明を事務仕事のように加えて済ますだけで、分詞構文利用の実態やその精神にまで深く踏み込んだ例は数少ないです。塾長は理系研究者としての経験と立場から、この様な点に対しても第三者的な切り込みを入れつつそろりと、いや濃厚に!、説明を加えて行きます。本シリーズの第5回目です。 British Council Learn English Grammar C1 grammar Participle clauseshttps://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/c1-grammar/participle-clauses『試験に出る英文法』 森一郎、青春出版社、1971年 第3章現在分詞・過去分詞 pp.48-53『チャート式 英文解釈』 鈴木進、数研出版、昭和51年、第2編文の構造上よりの解釈 第2章 句を中心としてここの基本的構成並びに(難解な)例文を幾つか参考にしていますが、塾長なりの視点から批判的検討を加え、また一部、より現代的な、或いはより正しい明確な表現となる様、書き換えたものも併記しています。https://ypir.lib.yamaguchi-u.ac.jp/bg/215/files/135479現代英語の分詞構文(その1) 一Anima1 Earmの分詞構文一福島一人 英米文学研究 20 巻 141-170 頁 1984-12 発行紀要論文 出版者 梅光女学院大学英米文学会[ISSN] 0288-0075*分詞構文の使用頻度の高い George Orwell, Animal Farm を素材として、全158用例についての分析を行って居ます。https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_verb_constructionhttps://ja.wikipedia.org/wiki/動詞連続構文 |
||
 |
 |
[英文句型介紹] 再談分詞構句一 participle clause revisited 1
余綺芳 2020/03/05 https://youtu.be/nXHaYac00pk
如果瞭解分詞構句,對於閲讀及寫作很有幇助。這影片強調分詞構句的形成及獨立分詞
構句用法等。
分詞を使った文の作り方を知っていれば、リーディングやライティングに役立ちます。
このビデオは、分詞構文の形成と独立分詞構文の使い方に重点を置いています。
主詞相同・両個動詞、即ち主語が一致していて動詞が2個ある文を後者を分詞化して and で
接続する方法を分詞構句(分詞構文)の1つの作り方だと紹介していますが、これは塾長の
言う疑似分詞構文の作り方の片方に大方一致します。この動画では他に副詞句作成を、続編
動画にて形容詞句作成も含めて分詞構文作成法としていますが、広義の分詞構文ですね。
He walked out of the room, and stammed the door behind him.
→He walked out of the room, stamming the door behind him.
彼は部屋から歩いて出たがドアをバタンと閉めた。これは2つの動作が同時に
では無く時間差を於いて起きた事を述べています。
 |
 |
|
B.等位接続詞の意味を含み、主文に対して後置し、順接・逆接の結果、或いは情報、を付け加える分詞構文(疑似分詞構文)1*この用法は、<本来の>副詞句を構成する分詞構文-従節の動詞を分詞化する-から派生して、等位節の動詞を分詞化する手法、はたまた関係代名詞を省略する方向に拡大した用法と言えるのかも知れません。*或いは、何でも後ろに添えてしまう英語の習性-これは付帯状況の同時性の記述-が時間差を置く事象にも拡大した結果なのかも知れません。*まぁ、従属接続詞に留まらず、等位接続詞、関係代名詞まで省略して分詞で繋げてしまう訳ですね。*逆に言えば、文法上の従属接続詞、等位接続詞、関係代名詞の区別無く、接続詞の類いは削除して分詞で繋いで仕舞おうとの英語使用者の意識の反映とも言えそうです。*実はこれが、分詞構文理解の本質にも見えます。*以下、意味用法から幾つかに分類していますが、分詞構文のご多分に漏れず、結果、連続動作、付帯状況、情報追加などに明確に分類できないところがあるのは勿論!です。1.結果を付け加える分詞構文*等位接続詞で接続される文は、主節、従属節の関係には無く、互いに対等です。*従って、後ろの文を簡略化して<分詞化>しても、前の文全体を修飾する副詞としての機能は元々無く、主文に対して副詞句として働くべき本来的な分詞構文(=狭義の分詞構文)ではありません。*従って、疑似分詞構文とでも呼称出来るでしょう。*同時発生・事象の併行を表す付帯状況-当然乍ら主文動詞と付帯状況の動詞とは時制がきっちり一致しています-とは意味合いが異なっている訳です。*これに利用される現在分詞 の意味上の主語は、単純に主文と同一の場合もありますし、前文(=主文)内容を指す場合もあります。*前者の場合は、次いで~した、の動作の単純な連続性(これも一種の結果ですが)を記述します。*しかるに後者の場合は、<そしてその事(今述べた事)が~と言う結果に繋がる、起こす、招く、可能にする>、などの、主文に対しての未来性、帰結の意味を強めます。*従って、これらの分詞構文は、共に、結果の分詞構文とも呼称出来るでしょう。*前者の用法-分詞の意味上の主語が主文主語に一致-では、一般的な動詞が利用可能ですが、後者-分詞の意味上の主語が主文内容に一致-の場合は結果を将来する意味の動詞、例えば、result in, lead to, cause, make, allow などが主に利用されます。*前者は、<, doing>→<, and [then] do/did/does>にサッと書き換えられます。*後者は、<, doing>→<, which (do/did/does)>、<, and that/this + (do/did/does) に変換出来ます。(疑似分詞構文である事を明確に示す為に、and doing と、元々 and を添える例もあります)*しかし文章が長く読みにくい場合は、前後者共に、新たに主語 (後者ではThat, This にする)を立てて別文として切り離すのも良い事です。*塾長も、後ろにだらだらと現在分詞が続けられる長い文に出会った時は、生徒達には、「即座に分割して新たに文を仕立てよ」、と指導しています。*実際、この用法は長々とした文を記述する傾向の書き手に好んで利用され、一層、文の解釈を困難にする例が多いからです。*換言すれば、短くて明確な繋りのある文をモノしようとの意識の薄い者-一種時代遅れの者達-に好まれる修辞法とも言えそうです。*某医学部の入試問題に利用された国内で発行される某有名英字新聞の文章が矢鱈に長く、後ろに修飾語句や関係代名詞、(疑似)分詞構文を用いて一体どこまで続けるのかと思うぐらいのものがあったのですが、これでは生徒達の手本にならないと感じ、こんな英語を書いてはダメだよと、反面教師的素材として指導した事もあります。*明確で高度な思考内容を伝達する道具としての英語の利点を問うことなく、文学的な古くさい修辞を弄して何でも詰め込んで長い文を作成することがインテリの証明だと、大きな勘違いをしているのでしょう。*しかし、この疑似分詞構文の用法自体には意味の曖昧性が無く、特に後者の用法は、一部の学術誌ではほぼ定型表現ながら使用が認められている場合があります。*まぁ、いわゆる狭義の分詞構文とは見做されていないとの話になります。<動作の連続・結果を表す現在分詞用法>とでも呼称した方が良さそうです。*順接であるか逆接であるかは文脈に因りますが、順接の場合が殆どです。----------------------------cf.https://grammarist.com/grammar/participle-clauses/このサイトでは結果として起きる動作 (actions happening consecutively) を示す用法として以下の文例を挙げています。Reading her quick explanation of adverbs, I thought I needed more extended video explanations.彼女の副詞に関する簡単な説明を読んで、私はもっと拡張したビデオ説明が必要だと思った。*これは、確かにAs a result of reading her quick explanation of adverbs, I thought I needed more extended video explanations.とも解釈出来ますが、after や理由の as の従属接続詞を利用して節に仕立てる事も出来ます。*即ち、副詞句を構成する分詞構文であり、本項で解説する、等位接続詞で連結される<結果の分詞構文>-必ず分詞表現が主文の後ろに並ぶ-とは全く別個のものです。*この様に、native 作成の文法解説を見ても、各人が個人的な見解、解釈を進めて開陳しているのが分詞構文解説の実態であり、native 自身が十分な検討無く、曖昧性の上に分詞構文を利用していることが窺えます。*これは、例えば言葉 as に対する文法解説動画やサイトと同じで、<語っている本人が十分に理解・整理しておらずに動画やサイトを作っているのでは無いか>と感じさせられるシーンと同じです。 |
||
 |
 |
The doctor constantly ignored the patient's feelings, resulting in bigger problems.
医者が患者の気持ちを無視し続けた結果、より大きな問題に発展してしまいました。
Wonderful Moment 2024年10月27日
The story comes from Season 2, Episode 18 of ER, which tells how the doctor constantly
ignored the patient's feelings, leading to bigger problems.
https://www.youtube.com/shorts/i_v1HlGUxz0
『ER』 のシーズン2、第18話からのワンシーンです。
resulting in は前文内容を意味上の主語に取り、<, which (do/did/does)>、
<, and that/this + (do/did/does) にサッと変換出来ます。広義の分詞構文用法とは言え
ますが、副詞句を形成しないゆえに、本来の意味での分詞構文とは言えません。
 |
 |
|
以下例文1a.単純な連続的動作を表す用法*<, doing> ⇔ <, and [then] do/did/does > に置き換えて理解します。He walked out of the room, and stammed the door behind him.(これはwalk と stam の2つの動作が時間差を於いて起きた事を述べています)→He walked out of the room, stamming the door behind him.彼は部屋から歩いて出、ドアをバタンと閉めた。The train left Tokyo at 7 p.m., reaching Osaka at just midnight.(left と reaching に同時性が無い事は明らかです)→ The train left Tokyo at 7 p.m., and it reached Osaka at just midnight.列車は午後7時に東京を出発し、大阪に到着したのはちょうど真夜中だった。But to the Greek architect, the setting of his temple was all important. He planned it, seeing it in a clear outline against sea or sky, determining its situation on plain, hilltop, or the wide plateau of an acropolis. (お茶大)しかし、ギリシアのその建築家にとっては、神殿の配置がすべてであった。彼は、神殿の造りを考え、海や空を背景にした神殿の輪郭をはっきりと見定め、平地や丘の上、あるいはアクロポリスの広い台地の上のその建ち位置を決定した。→But to the Greek architect, the setting of his temple was all important. He planned it, saw it in a clear outline against sea or sky, and determined its situation on plain, hilltop, or the wide plateau of an acropolis.しかし、ギリシアのその建築家にとっては、神殿の配置がすべてであった。彼は神殿を設計し、海や空を背景に神殿の輪郭をはっきりと描き、平地や丘の上、あるいはアクロポリスの広い台地の上での神殿の配置を決めた。*これらの動作が順番に時間差を置いて行われたと解釈出来ますが、大方それほど時間差を置かずに次々と plan, see, determine が進められたことが文脈から読み取れます。*第一に神殿を設計し、次に背景に浮かぶその姿を思い描き、最後に土地に建つ神殿の建ち位置を決定した、と読めるので、完全一致の同時間の出来事、即ち付帯状況とは考えられず、動作の連続を表すと考えます。*即ち、この3つの動詞は、時間差を表す and で接続されるものと考えて良いでしょう。*動作連続構文なる概念があり、1つの定義に基づけば 「等位接続・従属をはじめとした如何なる統語的依存関係の標識も伴わずに現れ、単一の述語として振る舞う動詞の連続と規定している。その意味は単一の出来事として概念化されており、音声的にもひとまとまりで発音される。すなわち、ポーズが現れがちな節の境界とは異なり、単一の節を成す動詞の境界においてイントネーションの休止は起こらない。」とされます。https://ja.wikipedia.org/wiki/動詞連続構文*上記分詞構文では、各分詞はおのおの別個の動作を表しており、単一の動作としては理解されません。この、動作連続構文とは全く異なるものですが、「等位接続・従属をはじめとした如何なる統語的依存関係の標識も伴わずに現れ」の箇所が該当し、ちょっと面白く感じました。*単一の出来事として概念化される、ことは、同時並行的に複数の動作がミックスして起こることを意味しますので、付帯状況の分詞構文に寧ろ近い様にも見えます。----------------------------*元々、and doing と、and を添えて表記される例(以下、George Orwell, Animal Farm から、福島一人氏の引用に拠る)In another moment the van was through it and rapidly disappearing down the road.次の瞬間、バンはそれを走り抜け、あっという間に道の彼方へと姿を消した。→ and rapidly disappeared...*最初から過去形で書けば足りていますが、書き手の好みで分詞を採用したのでしょう。1b.主文内容がもたらす結果を明示する用法*この場合は、<, doing > の意味上の主語は、前文内容であり、<, which (do/did/does)>、<, and that/this + (do/did/does) にサッと変換して理解します。*and doing と表記される例もあります。*多くの動詞が利用出来ますが、以下は良く見られる表現です。result inThe company announced a product as being offered for a limited time only, resulting in that item's rapid disappearance from shelves in grocerystores.その会社がある商品を期間限定で販売すると発表したが、その結果、その商品は食料品店の棚から急速に姿を消した。→The company announced a product as being offered for a l imited time only, which resulted in that item's rapid disappearance from shelves ingrocery stores.Once the water is moved into a low-temperature space, the held-in energy rapidly escapes, resulting in still more cooling.水が低温空間に移動すると、滞留していたエネルギーが急速に逃げ出し、さらに冷却が進む。→ Once the water is moved into a low-temperature space, the held-in energy rapidly escapes, and this results in still more cooling.→ Once the water is moved into a low-temperature space, the held-in energy rapidly escapes. This results in still more cooling. (別文仕立てに)causeTyphoon No. 17 made landfall in that city, causing severe flooding and destruction of farmland.台風17号はその市に上陸し、深刻な水害と農地の破壊をもたらした。→Typhoon No. 17 made landfall in that city, which caused severe flooding and destruction of farmland.reduceOur USB memory devices can be set with a double password, thereby significantly reducing the risk of information leakage in the event of loss.当社のUSB メモリーには二重のパスワードを設定出来るため、万一紛失しても情報漏逸の危険性を大幅に減少できる。→Our USB memory devices can be set with a double password, which significantly reduces the risk of information leakage in the event of loss.→Our USB memory devices can be set with a double password. This significantly reduces the risk of information leakage in the event of loss.(長いので2文に分割する)(続く) |
||
 |
 |