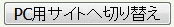英文読解から入試まで 完全マンツーマン指導
https://dictionary.cambridge.org/ja/dictionary/english/
塾長のコラム 2025年6月25日
 |
 |
|
分詞構文6 |
||
2025年6月25日 皆様、KVC Tokyo 英語塾 塾長 藤野 健です。 これまでのシリーズの中にてところどころ断片的に分詞構文についての説明を行って来てはいましたが、意外や纏めて解説した事は無く、本構文シリーズの1つに加えるのも悪くない、いや欠かす方が寧ろおかしいぐらいですね。学校英語の場でも入試に際しても、必ず解釈を問われるのが分詞構文ですので、その意味合い並びに成立をがっちりと把握しておくことは勿論大きな強み、得点源となります。長文読解などに於いて、文構造が把握出来ない、何を言っているのか不明で困る、などのシーンでは、分詞構文が使用されているかどうかをまず見抜くことがキモになりますし、その様な<ヒネた>文章ゆえ、-誰でも分かる英文を和訳させても点差が付かなくなる-和訳しなさいなどと設問が為されることになります。特に難関大学の入試では、with で始まる付帯状況を表す分詞構文の意味をどうやって日本語に好適に変換するのか、などに習熟しておく必要があるでしょう。この辺りは、扱い方、和訳の遣り方の型がありますので、知っておいて損な事は全くありません。余談ですが、これまで扱って来た、条件法、否定、比較、倒置、省略、挿入、強調表現などに加え、分詞構文、更には関係詞も我が懐中の物としておく- native の規定する英語習熟度のランキングで言うと C1 advanced level 以上に相当します-と、語彙の面は別として、大学入試のみならず英語圏での文章にはほぼ対応が出来ることになります。逆に言えば、英文読解の極意ここにあり、なのですが、英語とは或る意味単純明快な言語であるとも言えましょう。 いわゆる付帯状況や情報の追加説明を便利に表現出来る用法を除き、口語では利用されることは普通は見られませんが、基本的に non-fiction writing ではなく、fiction writing に利用される表現として、分詞構文は軽い記述の書き物、エッセイ、に始まり、重々しい文学作品に至るまでの幅広い範囲で頻用されます。non-fiction に於いては、例えば(少なくとも現行の)自然科学の学術雑誌では、編集部の方針で利用を禁じていることが殆どですし、分詞構文の或る特定の記述形式(文末に、カンマ+doing の形で文を延長する単純接続の分詞構文)のみOKを出す雑誌も存在します。何故かと言うと、本来的に明確な意味を持つ接続詞を用いて文を明確に記述すべきところ、論理結合子である肝心の接続詞、更には主語までを省略し、副詞句として主文に添える形が分詞構文だからです。詰まりは、文が簡潔になったのは良いが、意味合いに曖昧性を持ち込んでしまう大きな欠点を併せ持つのが分詞構文になります。別な見方をすれば、書き手側が本来的にどの接続詞を用いるべきかを意識することなく、<取り敢えず知的にも見えるしサラっとこの修辞法を用いて文を述べて繋いでしまおう>との意識の表れか、とも言えそうです。これでは、読者に対して揺るぎの無い明確性に立ち真実を伝えんとする学術論文の場では適当な表現法とは言えなくなるのは自明かと思います。言わば、口語では利用されず、文章中では formal などとされて頻用されるものの、厳密な意味合いを伝達する場では利用出来ない、との半端な性質を持つ表現になります。まぁ、文学的な修辞に近い立ち位置ですね-表現に曖昧性を含ませることが(少なくとも嘗ての)英語の文学性の1つの特徴だったのかと勘ぐりたくもなります・・・。この様な分詞構文の抱えるマイナス点を明確に説明する国内外の動画などは塾長は殆ど見たことがなく、鹿爪顔で分詞構文の一通りの説明を事務仕事のように加えて済ますだけで、分詞構文利用の実態やその精神にまで深く踏み込んだ例は数少ないです。塾長は理系研究者としての経験と立場から、この様な点に対しても第三者的な切り込みを入れつつそろりと、いや濃厚に!、説明を加えて行きます。本シリーズの第6回目です。 British Council Learn English Grammar C1 grammar Participle clauseshttps://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/c1-grammar/participle-clauses『試験に出る英文法』 森一郎、青春出版社、1971年 第3章現在分詞・過去分詞 pp.48-53『チャート式 英文解釈』 鈴木進、数研出版、昭和51年、第2編文の構造上よりの解釈 第2章 句を中心としてここの基本的構成並びに(難解な)例文を幾つか参考にしていますが、塾長なりの視点から批判的検討を加え、また一部、より現代的な、或いはより正しい明確な表現となる様、書き換えたものも併記しています。https://ypir.lib.yamaguchi-u.ac.jp/bg/215/files/135479現代英語の分詞構文(その1) 一Anima1 Earmの分詞構文一福島一人 英米文学研究 20 巻 141-170 頁 1984-12 発行紀要論文 出版者 梅光女学院大学英米文学会[ISSN] 0288-0075*分詞構文の使用頻度の高い George Orwell, Animal Farm,1945 を素材として、全158用例についての分析を行って居ます。https://ja.wikipedia.org/wiki/動物農場「とある農場(「マナー農場」)の動物たちが劣悪な農場主を追い出して理想的な共和国を築こうとするが、指導者の豚が独裁者と化し、恐怖政治へ変貌していく過程を描く。人間を豚や馬などの動物に見立てることにより、民主主義が全体主義や権威主義へと陥る危険性、革命が独裁体制と専制政治によって裏切られ、革命以前よりも悪くなっていく過程を痛烈かつ寓話的に描いた物語であり、ロシア革命とソビエト連邦を理想の国とみなすような「ソビエト神話」への警鐘であった。」Wikipedia contributors. "動物農場." Wikipedia. Wikipedia, 21Sep. 2024. Web. 12 Mar. 2025.*以下より英語原版が全文無料で入手出来ます:https://archive.org/details/AnimalFarm-English-GeorgeOrwellhttps://www.marxists.org/subject/art/literature/children/texts/orwell/animal-farm/index.htm*一言一句を読解すると英語力が格段に上がるでしょう。*以下より和訳版が無料で入手出来ます:https://open-shelf.appspot.com/AnimalFarm/index.htmlhttps://en.wikipedia.org/wiki/George_Orwellhttps://ja.wikipedia.org/wiki/ジョージ・オーウェル |
||
 |
 |
Animal Farm in 60 Seconds: Orwell's Timeless Tale of Power and Corruption
2024年7月20日 https://www.youtube.com/shorts/CAHYVBFHeNQ
"1984" と並び Orwell の有名作です。人間性の本質を良く衝いていると感じます。
塾長は、ウィリアム・ゴールディング (1983年ノーベル文学賞受賞) 著の
『蠅の王』 Lord of the Flies, 1954 を連想します。
【ゆっくり解説】世界的に有名な写真の裏話 「消されたトロツキー」
2025年5月26日
https://www.youtube.com/shorts/UxhPi1Qlgjg
因みに顔貌から分かりますが、スターリンは非ロシア人であり、グルジア人です。
 |
 |
|
B.等位接続詞の意味を含み、主文に対して後置し、順接・逆接の結果、或いは情報、を付け加える分詞構文(疑似分詞構文)21.結果を付け加える分詞構文(続き)1b.主文内容がもたらす結果を明示する用法*この場合は、<, doing > の意味上の主語は、前文内容であり、<, which (do/did/does)>、<, and that/this + (do/did/does) にサッと変換して理解します。*and doing と表記される例もあります。*多くの動詞-動作動詞-が利用出来ますが、以下は良く見られる表現です。lead toThe necessary costs were higher than expected, leading to considerable losses.必要経費は予想より高くなり、かなりの損失に繋がった。→ The necessary costs were higher than expected, which led to considerable losses.The president continued his years of profligate management, leading to the company's bankruptcy.社長は長年に亘る放漫な経営を続けたが、会社の破産を招いた。→ The president continued his years of profligate management, which led to the company's bankruptcy.leaveMoments later a bomb exploded, leaving ten people dead and many injured.その直後、爆弾が爆発し、10人が死亡、多数の負傷者が出た。→ Moments later a bomb exploded, whch left ten people dead and many injured.makeThe processing power of computers has improved significantly over the past decade, making it easier for amateurs to edit video.パソコンの処理能力が過去10年の間に著しく向上し、アマチュアが動画編集することを容易にした。→The processing power of computers has improved significantly over the past decade, which made it easier for amateurs to edit video.allowThe processing power of computers has improved significantly over the past decade, allowing amateurs to edit video more easily.この10年でコンピューターの処理能力は格段に向上し、アマチュアでも簡単にビデオ編集ができるようになった。→The processing power of computers has improved significantly over the past decade, which allowed amateurs to edit video more easily.→The processing power of computers has improved significantly over the past decade. This allowed amateurs to edit video more easily.injureThe building collapsed, injuring the people inside.その建物が崩壊し、その結果、中にいた人々が負傷した。→ The building collapsed, which injured the people inside.succeed(以下、George Orwell, Animal Farm, 1945 から、福島一人氏の引用に拠る)He...would stand staring at the letters with his ears back, sometimes shaking his forelock,trying all his might to remember what came next andnever succeeding.彼は耳をそばだてて文字を見つめていたものである。時には前髪を振り乱し、次に何が来るのか、必死に思い出そうとしながら。しかし、それは決して成功しなかった*shaking と trying は同時性の付帯状況を表しますが、and succeeding は前文内容の一部であるto remember what came next が結果として成功しなかったことを表しています。→ <, and that never succeeded>, 或いは <, which never succeeded>*前2つの同時性を示す分詞との区別を明瞭にすべく、and を用いたと思われます。*まぁ、George Orwell の Animal Farm 中には全158例の分詞構文が使用されているとのことですが、彼の分詞構文多用<癖>には恐れ入ります!*猫も杓子も!分詞構文との具合で・・・。*Animal Farm の全文は以下より無料で入手出来ます:https://archive.org/details/AnimalFarm-English-GeorgeOrwellhttps://www.marxists.org/subject/art/literature/children/texts/orwell/animal-farm/index.htm |
||
 |
 |
Defining and Non-Defining Relative Clauses - English Grammar Lesson
Oxford English Now 2019/07/26 https://youtu.be/a_mFlafGyy8
関係節の制限用法と非制限用法の違いについてここで一度復習して下さい。
毎度の如くで大変分かりやすい解説をして呉れます。
non -defining の方は、extra information を追加しますが、それを削除しても
文章は成立します。
それに対し、defining の方は削除すると文章の幹が失われてしまいます。
non -defining の方はコンマを前に添え、制限用法と大方同じ関係詞が利用
出来ますが、that と why は利用出来ません。
Non-defining relative clauses | English grammar rules
Crown Academy of English 2016/03/21
https://youtu.be/_B8BRYoJJ6M
更にこちらの動画でダメ押しで確認して下さい!
15:30 から、A special use of "which"と称して、前文内容を
先行詞とする用法が紹介されます。この用法は native 一般人には
耳慣れない special なものに感じられると言う事ですね。
 |
 |
|
2.情報を付け加える分詞構文*主文内容全体或いはその一部の文言に対し、追加的に説明を単純に加えたいのであれば、適当な構文などを利用して記述(関係代名詞の非制限用法など)することが出来ますが、その明確な記述を<端折り>、分詞を利用して繋げた類いの文を見ます。*<, which> や<, who>を用いて書き直せば<復元>自体は容易ですが、これを行う判断に時間ロスしますので、 他の分詞構文同様に、文学的な修辞効果を意図するなど以外では、やはり使用を基本的に控えるべきと感じます。*情報を追加する点に於いて、非制限用法の関係代名詞と極めて誓い関係にある、と言う次第です。*最初から、非制限用法の <, which> や <, who> などを使って明確に記述すれば non-native には分かりやすく助かるのですが。*副詞句としての機能は持たず、狭義の分詞構文には該当しません。*単なる同格文言の挿入構文、或いは分詞を持ちいての後置修飾と差がない場合もあります。そうなると文法的に分詞構文と名乗るべきか、区別すべきなのかの問題も浮上しますね。*まぁ、分詞を使った表現用法には違いはありません。--------------------------------------------------*以下、関係代名詞の非制限用法を使った英文を分詞構文化してみましたが、前後を比較し、その妥当性を検討して下さい。*迷わずに元に戻せるのであれば、その分詞構文化はまだ妥当と言うことになります。前文の1部の名詞を先行詞として持つものThey passed old villages, some of which were deserted and forlorn.→ They passed old villages, some of them (being) deserted and forlorn.彼らは古い村を通り過ぎたが、中には荒れ果て寂れた村もあった。There are a lot of museums in London, the biggest of which is the British Museum.→There are a lot of museums in London, the biggest of them being the British Museum.ロンドンにはたくさんの博物館があるが、その中でも最大のものは大英博物館だ。https://www.thoughtco.com/nonrestrictive-relative-clause-1691350*以下の、分詞構文化する前の非制限用法の元の英文はここから借用しています。Kaylee, who just graduated from high school, is an accomplished figure skater→Kaylee, just having graduated from high school, is anaccomplished figure skater高校を卒業したばかりのケイリーは、フィギュアスケートの名選手だ。.The paint, which Mary bought at the hardware store, wasbright red.メアリーが金物屋で買ったペンキは真っ赤だった。→× The paint, Mary having bought at the hardware store,was bright red.(奇妙な英文になり、わざわざ分詞構文化する意味がありません)Ms. Newmar, who lives next door, claims to be a Martian.→ Ms. Newmar, living next door, claims to be a Martian.隣に住むニューマーさんは自分が火星人だと言っている。For a balloon to float, it must be filled with helium, which is lighter than the air around it.→ For a balloon to float, it must be filled with helium, being lighter than the air around it.風船が浮くには、周りの空気より軽いヘリウムを入れなければならない。Besides the bookcase in the living room, which was always called 'the library,' there were the encyclopedia tables and dictionary stand under windows in our dining room. (Welty 1984).→ Besides the bookcase in the living room, always called 'the library,' there were the encyclopedia tables and dictionary stand under windows in our dining room.いつも "図書館 "と呼ばれていたリビングルームの本棚のほかに、ダイニングルームの窓の下には百科事典テーブルと辞書スタンドがあった。The United States, which presents itself as a global beacon of opportunity and prosperity, is quickly becoming a low-wage nation. (Soni 2013).→ The United States, presenting itself as a global beacon of opportunity and prosperity, is quickly becoming a low-wage nation.チャンスと繁栄の世界的な烽火のように見えるアメリカは、急速に低賃金国家になりつつある。Eugene Meyer, who was thirty-two years old, had been in business for himself for only a few years, but had already made several million dollars. (Graham 1997).→ Eugene Meyer, thirty-two years old, had been in business for himself for only a few years, but had already made several million dollars,ユージン・メイヤーは32歳で、起業してまだ数年しか経っていなかったが、すでに数百万ドルを稼いでいた。Dragonflies kill their prey in the air and eat it on the wing. They feed on aerial plankton, which consists of any sort of small living thing that happens to be aloft-mosquitoes, midges, moths, flies, and ballooning spiders. (Preston 2012).→ Dragonflies kill their prey in the air and eat it on the wing. They feed on aerial plankton, consisting of any sort of small living thing that happens to be aloft-mosquitoes, midges, moths, flies, and ballooning spiders.トンボは空中で獲物を殺し、翼の上で食べる。空中浮遊物をトンボは餌としているが、それらは蚊、小バエ、蛾、ハエ、空中飛行するクモなど、あらゆる小さなものである。I saw through the front blinds, which my mother always kept at a half-slant-'inviting but discreet'-that Grace Tarking, who lived down the street and went to a private school, was walking with ankle weights strapped to her feet. (Sebold 2002).→ I saw through the front blinds, my mother always keeping at a half-slant-'inviting but discreet'-that Grace Tarking, living down the street and going to a private school, was walking with ankle weights strapped to her feet.母が「誘うような、でも控えめな」様にいつも半分斜めにしていた正面のブラインドの隙間から、通りの先に住んで私立学校に通うグレース・ターキングが足首に重りをつけて歩いているのが見えた。 セボルド2002)。(動詞 ing 形が連続し好ましくありません。元の文の方が適切です。)A raw new development begins on the other side of my mother’s meadow, which she has not been able to mow this fall, since her injuries prevent her from getting up on the tractor. (Updike 1989).→ A raw new development begins on the other side of my mother’s meadow, she having not been able to mow this fall, since her injuries prevented her from getting up on the tractor.母の草地の反対側では、生々しい新しい展開が始まっている。この秋、母は怪我でトラクターに乗れないため、草刈りをすることができなかった。(無理遣り分詞構文化しましたが、そうする意味がなく、元のままが良好です。)-----------------------------------------------前文内容を先行詞として持つものNotre Dame Law Review (https://scholarship.law.nd.edu/ndlr)Three Concepts of Dignity in Constitutional Law 憲法における尊厳の3つの概念(https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1056&context=ndlr)Authors: Neomi Rao(https://scholarship.law.nd.edu/do/search/?q=author%3A%22Neomi%20Rao%22&start=0&context=4151206)の199頁に以下の文例が見られます:These disparate thinkers connect the inherent dignity of man to his distinctly human qualities, illustrated by comparing man with other animals and distinguishing man as the highest of God’s creatures.この文は、These disparate thinkers connect the inherent dignity of man to his distinctly human qualities,これらの互いに似ても似つかぬ思想家たちは、人間の内在的尊厳を人間特有の資質と結びつけているillustrated by comparing man with other animals and distinguishing man as the highest of God’s creatures.人間を他の動物と比較し、人間を神の被造物の中で最も高い存在として区別することで説明されるの2部分から構成されています。意味内容から illustrated by 以下は前文内容全体に掛かるものと判断され、本来的には、非制限用法の関係代名詞 which (先行詞は前文内容になります)を用いて、These disparate thinkers connect the inherent dignity of man to his distinctly human qualities, which is illustrated by comparing man with other animals and distinguishing man as the highest of God’s creatures.これらの異質な思想家たちは、人間固有の尊厳を、彼のはっきりとした人間的資質と結びつけている。そしてこのことは、人間を他の動物と比較し、人間を神の被造物の中で最高のものとして区別することによって示されている。とすれば明確ですが、which を省いて分詞化し<, being illustrated >とし、更には being を省略した構造だと判断可能です。*前文内容を先行詞として、それに動作動詞を繋げて結果を示す用法を、上の、<1b.主文内容がもたらす結果を明示する用法>にて扱いましたが、こちらは、受動態が続き、状態、追加説明を表す色合いが強くなりますね。*関係代名詞 which を利用せずに、過去分詞でつなぐ文は、意味は取れるものの、普通は目にしない文形式ではと思います。*破格であるとまでは強くは述べませんが、which を利用して欲しいところですね。*過去分詞 illustrated で繋ぐと、それが前文中の特定名詞に掛かる(過去分詞の形容詞用法)のかと読み手を惑わせるからです。*カンマの後ろに過去分詞が続いた場合は、取り敢えずは whichis/was などをさっと挿入してみて下さい。2文に分けた上で後ろを能動態化して、These disparate thinkers connect the inherent dignity of man to his distinctly human qualities, illustrating this by comparing man with other animals and distinguishing man as the highest of God’s creatures.→These disparate thinkers connect the inherent dignity of man to his distinctly human qualities.They illustrate this by comparing man with other animals and distinguishing man as the highest of God’s creatures.などと記述しても明確でしょう。 |
||
 |
 |