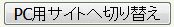英文読解から入試まで 完全マンツーマン指導
https://dictionary.cambridge.org/ja/dictionary/english/
塾長のコラム 2025年9月20日
 |
 |
|
その他の<構文>12 |
||
2025年9月20日 皆様、KVC Tokyo 英語塾 塾長 藤野 健です。 これまで、日本の文部科学省の学習要項に採りあげられている一通りの構文形式(特殊構文)について解説を加えて来ました。実は、言葉とは生き物ですので、新たな一定の勢力を持つ様式が世に広まれば、それが新たな構文形式として広く認知される筈ですし、実際、現況に於いてあまり注目されていない類いの構文形式も存在しています。これらは学校に於いて明確なカタチで学習指導を受けるものではないものの、実は日常的に頻用されるものがあり、或いは文学作品の中などにも散見されもします。学校英語としてまともに習うことが無い或いは少ないが故に、どうやって文法的に解釈すべきなのか、受験生などの頭を毎度悩まさせもすることでしょう。意味は分かるが文法的にどの様に理解すべきか判断に困る表現-破格ではないのかとの疑問を招く-も実際のところ少なくはありません。 これまで続けて来た構文ネタの1つの括りとして、このような、市井の日本人には明確にその名を知られていない<特殊の上を行く構文>-しかし一定量の英文に触れていれば必ずお目に掛かる筈の<構文>-について整理がてら触れていきましょう。尤も、文法面での解釈については研究者間で必ずしも見解の一致を見ているとは限らないものも含まれますし、その命名分類も恣意的な視点に立つものもあります。native 一般人がその用語、命名を知らず、英語学者が主だって分類命名している概念も存在します。これらの文章構造に対し、それはどの様なシーンや意味合いで使われるのかを分析・考察する類いの学術論文も多々あり、その考察や<新理論>を批判精神に乏しく丸ごと引き継いで日本の英語学者が仕事を始める展開-大学の英語の先生とはこんなことでメシ喰っているのか!-も垣間見ることも出来ます。ここで<構文>と括弧を付けているのは、実は構文そのものとは言えず、寧ろ動詞の機能に付いての分類、即ち動詞型の分類が先に立つものであるからです。・・・ざっとこの様な経緯もあり、学校英語では指導の骨幹としては明確には扱われないとも言えますが、試験(入試)に出して置いて生徒を悩ませるぐらいなら何故最初から定義を与え、簡略で構わないので教えないのかとの疑問も生じますね。まぁ、塾長のコラムをお読みのハイクラスの方々には耳に入れて置いて損なことは全くありません。その第12回目となります。 二重目的構文と与格構文をめぐって -構文指導における理論と実践- 中川右也https://www.chart.co.jp/subject/eigo/cnw/56/56-6.pdf英語の二重目的語構文と与格構文に関する一考察 高橋直子名古屋外国語大学外国語学部紀要 = Journal of School of Foreign Languages, Nagoya University of Foreign Studies 41 109-126, 2011-08https://nufs-nuas.repo.nii.ac.jp/records/335https://en.wikipedia.org/wiki/Ditransitive_verbhttps://ja.wikipedia.org/wiki/二重他動詞https://en.wikipedia.org/wiki/Dative_shift大庭幸男 『英語構文を探求する』 開拓社 2011中村 捷、金子 義明 『英語の主要構文-構文から見た英文法』ISBN 9784327401290 研究社 2002https://www.collinsdictionary.com/jp/dictionary/english/owehttps://en.wiktionary.org/wiki/owehttps://www.etymonline.com/word/owehttps://hapaeikaiwa.com/blog/2016/05/12/「to-me」と「for-me」の違い/Hapa Eikaiwa |
||
 |
 |
Verbs with 2 Objects - Indirect and Direct Objects - English Grammar
Teachers Mark and Matt 2021/01/12に公開済み
https://youtu.be/qzKPIAEEA4s
to 与格、for 与格のいずれになるのか理由が分からないと発言していますが、
native 自身が個々の動詞の用法を1つずつ成長の過程で習得しているだけで
あり、一般的な文法法則として理解している訳では無いことを示す一例ですね。
日本人も同様にして日本語が話せるようになりますが、必ずしも文法を把握して
いる訳ではないのと同じです。
Different Ways To Use VERBS WITH TWO OBJECTS In English
Englogic - Logic Of English 2022/05/11 LONDON
https://youtu.be/gS_2OcuBU4s
優れた内容の動画ですが何故か再生数が少ないです。
 |
 |
|
二重目的語構文 Double Object Construction*この構文-と言うよりは文型-自体は何ら特殊なものではなく、学校英語で言うところの第4文型 S+V+IO+DO に過ぎません。(IO = indirect object 間接目的語、DO =direct object 直接目的語)*この構文の詳細な性質を語れば可なりの長丁場になりますが、ここではザッと概要だけに触れます。*皆様のアタマの中のモヤモヤ感を少しでも減らすことが主目的です。*中学英語に登場する文型ですので一見敷居は低く見えますが、奥はそこそこ深いですね。*これまでご紹介してきた真の意味での特殊構文とは異なり、<参入障壁>が低い分だけ、discussion も活発であり、web 上でも数多くのサイトを見つける事が出来ます。*それだけ、特に学校教員含め、世間の耳目を集めているトピックと言う事になるのでしょう。*これらの discussion の焦点は、S+V+IO+DO の文型を S+V+DO+ to/for IO のいずれに書き換え可能なのか、その根拠は何か、その逆は取れるのか、またこの書き換えに際してニュアンスの違いが発生しないのか、にほぼ絞られています。*おそらく、これらのサイトや論術の多くは、生徒からの質問に対し、どう指導すべきかに頭を悩ませている現場の英語教員自らが勉強して作成した regume、或いは、彼らを対象とする英語指導者の指南になります。*例えば、教員としての中川右也氏執筆の記事 『二重目的構文と与格構文をめぐって -構文指導における理論と実践-』https://www.chart.co.jp/subject/eigo/cnw/56/56-6.pdfでは、冒頭に以下の様に記されています:「2. 二重目的語構文から与格構文への書き換え教育現場では、しばしば二重目的語構文から与格構文への書き換え問題を取り上げる。その際には.通例. to与格構文をとる動詞を give型、for 与格構文をとる動詞を buy 型と分類し、方向性を含意する動詞 は give 型 に、受益性を含意する 動詞は buy 型になると教えて,学習者への定着をはかる。しかし、この教え方の問題点は、例えば「教えてあげる」という日本語に引きずられて、slow learners が teach などの動詞をも受益性を含意する動詞と見なしてしまう場合があるということで ある。そうした slow learners の蹟きを避けるためにも、 give 型動詞は三項動詞,つまり、相手 (IO) の存在なしでは行為が行えない動詞であり、buy型動詞は二項動詞にもなりえる動詞、つまり、一人でもその行為を行うことが可能な動詞であると教えた方が効果的であると考えられる。」*この、二項動詞の表現が可能で有れば S+V+IO+DO → S+V+DO for IO. が取れ、不可能であればS+V+DO for IO.となる、との区別法は you tube 動画の解説などでも普通に目にする指導法となっていますし、塾長もこの指導法で特に間違いはないと感じています。*実際のところ、中学生程度の初学者に対しては、「単にAからBへの物資の移動、情報の伝達が行われる動詞 は give 型 に、特にあなたの為に~する(~の為に~を行う: 行為)の意味の動詞は buy 型になる」と、塾長も過去、拙宅近傍の補習主体の個別指導塾にて指導して来ました。*しかしこれだと、上記中川右也氏が指摘されている様に、どうしても曖昧性を排除出来ません。*上で与格と言う表現を用いていますが、これは語尾に日本語の助詞 「に」の意味の活用語尾を含む一語を指します。*英語では与格の格変化を失い、<方向性、対象性を含む前置詞+目的格>の組み合わせ全体が、与格に相当します。それらを前置詞との組み合わせから、to 与格、for 与格などと便宜上呼称していることになります。*詰まりは、ここでは前置詞は日本語の助詞に近い機能を持つことになりますね*この様な二重目的語構文から与格構文への書き換え(与格移動 dative shift)、 或いは2者間の書き換え(与格交替 dative alternation) の問題以外にも、意外や知られていない細かなこともあるのですが、それもこのコラムにてやや深掘りして進めて行きます。*二重目的語構文に関しては、大庭幸男氏が 『英語構文を探求する』 開拓社 2011 にて、70頁を割いて詳細な解析を行っていますので、興味のある方はご一読下さい。---------------------------------------------------二重目的構文を取る動詞以下の2つの条件を満たす動詞が二重目的語動詞になり、SVOO文型を作る事が出来ます。1.基本的に単音節から成る短い発音の動詞 (ラテン語由来の<高級>単語はほぼ該当しません)一般に、原語(アングロサクソン語)の動詞は 二重目的語構文を許しますが、ラテン語の動詞は許しません。これは、語源的な条件というよりも、動詞の発音上の問題が主な原因であると考えられています。英語原語の動詞は、ラテン語動詞によく見られる複数の音節に対して、単一の音節を持つことが多く、音韻学的特性から二重目的語構文の成立を許していると考えられてます。*俗ラテン語の1つであるフランス語では二重目的構文は取りません。Je donne le stylo a Pierre. わたしはピエールにペンをあげる。= I give the pen to Pierre.Je donne Pierre le stylo.×但し、目的語を代名詞にすると、2つの目的語を繋げて書く文は取れ、Je le lui donne. は成立しますが、英語で言うところの二重目的語構文とは性質が異なります。*(日本の) フランス語の指導者も英語の二重目的語構文との意味合いの違いが分かっていないままに、<二重目的語>の用語を使っている様に見受けられます。*これは、英語の場合と異なり、所有者、被所有者の関係にない2つの代名詞目的語にも広く使われる形式です。2.S+V+IO+DOの関係に於いて、IOがDOを所有する(動作の結果として所有することになる)意味合いを持つ動詞子供が二重目的構文を習得する過程で、最初は様々な動詞にて不文となる英文を話しますが、やがては、2つの目的語間の、所有者、被所有者の関係に(無意識的ではあっても)気が付き、正しい表現が可能となって行きます。尤も、これは法則性を一般化して獲得すると言うよりは、個々の単語の扱い方を獲得しているとの色合いが強いとの指摘もあります。まぁ、言語学習の積み重ねですね。*所有、被所有の関係から、利用される動詞は、与える giving, 連絡する communicating, 作る creating, 送る sending, 得る obtaining の意味の動詞になります。それらの動詞の内、*S+V +DO の形で文が成立不可能 (三項動詞)→ S+V+DO+ to +IO に変形可能*S+V +DO の形で文が成立可能 (二項動詞)→ S+V+DO+ for+IO に変形可能*三項動詞とは平たく言えば、文の成立には、動作主、対象物、受領者が必須の動詞です。SVO+to 受領者になります。*二項動詞とは、動作主、対象物だけでも文が成立する動詞のことです。SVO+ for 受益者になります。*上記<法則>を知っておくだけでも大きな力になる筈です。*これで中学生からの質問に対してもキチンと説明出来ますね。 |
||
 |
 |
Barbra Streisand - Woman In Love With Lyrics
ARBI NORA 2015/09/10 https://youtu.be/qI1WcylNEuY
I turn away from the wall/ I stumble and fall, but I give you it all
私は壁から向き直り、つまずき、転びながらも、すべてをあなたに捧げる。
文法的には直接目的語が代名詞の場合はSV+IO+DO の文型は好ましくないとされ、
I give you it all → I give it all to you とすべきと一瞬思いますが、
it all = everything / all things ですので問題なく利用されます。
rylics も易しいので、この名曲を是非カラオケで歌える様にして下さい!
Borrow と Rent の使い分け。
藤原ジェイ | 英語の先生 2025年 5月15日
https://www.youtube.com/watch?v=LC_6g6KEyoA
lend はブツそのものを貸す、の意味で lend money 金を貸すの表現は
極めて一般的です。rent は使用料を支払わせてモノを貸す、ですね。
ネイティブ2人で「To me」と「For me」の違いについて触れてみた
Hapa 英会話 2021/09/29 https://youtu.be/Br-P27tNxN0
二重目的語構文は to 与格構文、for 与格構文のいずれに書き換えられるかは
動詞に拠り決定していますが、動詞と結び付きの弱いケースでは to 或いは for
の使用は native も意識すること無くいずれも使用しています。但し、意味的に
to のみ、for のみしか利用出来ない場合もあります。
 |
 |
|
以下一部の動詞例:*全て、2つの目的語の間で、物や情報の遣り取りが行われることにご注意下さい。give 与えるLucy gave Mary the book.Lucy gave the book. ×⇔Lucy gave the book to Mary..*但し、直接目的語が代名詞となる場合は、このSVOO構文は取れなくなります。Lucy gave Mary the book.Lucy gave her the book. ◯Lucy gave Mary it. ×.*Lucy gave it to Mary..◯*Lucy gave it to her.◯Lucy gave her it. ×.また、Lucy gave the book to her. これは文法的には正しいのですが、Lucy gave her the book. と言うのが標準的です。cf. Barbra Streisand の Woman In Love の歌詞にI turn away from the wall/ I stumble and fall, but I give youit all私は壁から向き直り、つまずき、転びながらも、すべてをあなたに捧げるこれは I give you it all → I give it all to you とすべきと一瞬思いますが、it all = everything / all things ですので問題なく利用されます。*2つの目的語の間に副詞を入れる事はできません。Lucy gave Mary carefully the book.×Lucy gave Mary the book carefully .◯*間接目的語が長い場合は、SVOO 文型は避けます。Lucy gave the policeman standing by the door her ticket. ×Lucy gave her ticket to the policeman standing by the door. ◯Lucy donated/contributed Mary the book.× (単音節ではない動詞)Lucy donated/contributed the book to Mary .◯Lucy offered Mary the book.Lucy offered the book to Mary..ルーシーはメアリーに本を差し出した。Your portrait doesn't do you justice.= Your portrait doesn't give you justice.あなたの肖像画はあなたを正当に評価していない。→君は写真より実物の方がずっといいね。I'm in a bit of a bind, and I need you to do me a favor.ちょっと困っているんだけど、君に頼みがあるんだ。= I'm in a bit of a bind, and I need you to give me a favor.do 効果、結果を与えるdo someone/something good/harm= to have a harmful or good result or effect有害な、あるいは良い結果や効果をもたらす。It'll do you good to take a rest.君は休んだ方がいい。The publicity did her career no harm.その宣伝は彼女のキャリアに何の害も与えなかった。= Her career did not suffer any harm from publicity.lend owe 貸し借りするLucy lent Mary a large sum of money.ルーシーはメアリーに大金を貸した。= Lucy lent a large sum of money to Mary.(借りたものであるにせよMary は大金を握って居ます)Mary owed Lucy a large sum of money.メアリーはルーシーに多額の借金があった。= Lucy owed a large sum of money to Mary.(Lucy が多額の金を所有しています)cf. owe someone something = owe something to someone= someone lend money to you and you have not yet repay or paid it back人に金を借りて返していない、借金している、借りている、(転じて)恩義がある、~のお蔭だ*owe はちょっと意味の取りにくい動詞ですね。*= to have to repay, be indebted for 返さねばならない、負債を負っている*should pay, should repay にサッと置き換えると意味が掴めます。*動詞 owe の元々の過去形は ought です。Lucy lent Mary a large sum of money.(大金を貸したが返却の有無については触れていない)Lucy lent Mary a large sum of money, and Mary has not yet paid it back to Lucy.(大金を貸したが返却されていない)= Mary owes a large sum of money to Lucy.Perhaps we owe these people more respect.おそらく私たちは、この人たちにもっと敬意を払う義務がある。= Perhaps we should pay more respect to these people.I owe you an apology. You must have found my attitude very annoying.私はあなたに謝らなければならない。あなたは私の態度がとても腹立たしかったに違いない。I owe her a big debt of gratitude.僕は彼女には大きな恩義がある。= She has done me a great favor and I want to repay it.(精神的に彼女の恩義に報いねばならないと思って居る)keep 取っておくLucy kept something to eat and drink for all the people who arrived late.Lucy kept them something to eat and drink.ルーシーは遅れて到着した人たち全員に何か食べたり飲んだりできるものを用意しておいた。Lucy booked Mary a table at the restaurant.Lucy booked a table for Mary at the restaurant.ルーシーはメアリーにレストランのテーブルを予約した。Lucy promised Mary a car for her birthday.Lucy promised a car to Mary for her birthdayルーシーはメアリーの誕生日に車を贈ると約束した。(promise は単音節ではありませんが SVOO 文型を取る珍しい例です)buy 買い与えるLucy bought Mary some food.Lucy bought some food. ◯⇔Lucy bought some food for Mary..◯Lucy purchased Mary some food .×(単音節ではない動詞)Lucy purchased some food for Mary ◯Lucy got Mary some food. ◯Lucy obtained/collected Mary some food. ×(単音節ではない動詞)Lucy obtained/collected some food for Mary ◯.Lucy sold Mary the book.tell 言葉で伝えるLucy told Mary the news.Lucy told the news.×⇔Lucy told the news to Mary.Lucy explained/announced/reported Mary the news. × (単音節ではない動詞)Lucy explained/announced/reported the news to Mary. ◯Lucy read Mary another story.Lucy read another story for Mary.ルーシーはメアリーに別の物語を読んであげた。Lucy wrote Mary a letter.Lucy wrote a letter to Mary(ここの write は<手紙を書いて送る>、の意味であり、本を執筆する、の意味ではありません)Lucy wrote Mary a story.Lucy wrote a story for Mary.(こちらの write は執筆する、の意味です)Lucy sang Mary the song.Lucy sang the song for Maryshow 示すLucy showed Mary her answer.Lucy showed her answer to Mary.Lucy exposed Mary her answer × (単音節ではない動詞)Lucy exposed her answer to Mary ◯Lucy found Mary the book.Lucy found the book for Mary.ルーシーはメアリーに本を見つけた。bake 作るLucy baked Mary a cake.Lucy baked a cake. ◯⇔Lucy baked a cake for Mary.Lucy made Mary a sandwichLucy made all the children toys.Lucy cooked Mary a chinese dish.Lucy constructed/designed/created Mary a cake. × (単音節ではない動詞)Lucy constructed/designed/created a cake for Mary. ◯Lucy poured Mary another drink.Lucy poured another drink for Mary.ルーシーはメアリーに飲み物をもう一杯注いだ。ship 物を送るLucy shipped Mary a parcel.Lucy shipped a parcel. ×⇔Lucy shipped a parcel to Mary.ルーシーはメアリーに小包を発送した。Lucy sent Mary a letterLucy mailed Mary a letterLucy is posting Mary a cheque tonight.ルーシーは今夜メアリーに小切手を送ります。If I write a letter, would you post it for me?私が手紙を書いたら、投函してくれますか?(この post はsend の意味ではなく、投函する、の単なる動作を表します)Lucy took Mary the book.Lucy took the book to Mary.ルーシーはその本をメアリーのところに持って行った。Lucy brought Mary the book.Lucy brought the book to Mary.ルーシーはその本をメアリーのところに持って来た。(take 相手のところに持って行く vs. bring 相手のところに持って来る)Lucy handed Mary a little rectangle of white paper.Lucy handed a little rectangle of white paper to Mary.ルーシーはメアリーに四角い小さな白い紙を手渡した。Lucy passed Mary the booksLucy passed the books to Mary.ルーシーはメアリーに本を渡した。Lucy tossed/ threw Mary the ballルーシーはメアリーにボールを投げた。二重目的構文を構成しない単音節動詞の例*2つの目的語間に所有、被所有の関係がありません。Lucy washed the dishes for Mary. ◯Lucy washed Mary the dishes × (Mary は dishes を所有しない)ルーシーはメアリーのために皿を洗った。Lucy drove the car to Chicago. ◯ILucy drove Chicago the car. × (Chicago は car を所有しない)ルーシーはシカゴまで車を運転した。Lucy drove the car for Mary. ◯Lucy drove Mary the car. × (Lucy は car を所有しない)ルーシーはメアリーのために車を運転した。---------------------------------------------------cf. 「To me」と「For me」の違いhttps://hapaeikaiwa.com/blog/2016/05/12/「to-me」と「for-me」の違い/このコラムの執筆者の Jun さんに拠ると、・Family is important to me.(私にとって家族は大事です。)※家族は自分の人生において大事な存在と考えている。*「To me」は一般的な観点や立場による「私にとって」・Family is important for me.(私にとって家族の存在は大切です。)※家族の存在によって何らかの恩恵を受けているので大事と考えている。*「For me」は目的や目標を遂行するための「私にとって」→ Family is important for me を because... で繋げるのが自然、とあります。*to で、単純な受領者を表し、for で受益者であることを強調すると考えるのも良さそうですね。*意見を述べる意味合いには to me を使うが、文章の頭で用いられることが多い。・To me, Japanese curry is better than Indian curry.(私としては、インドのカレーより日本のカレーの方が美味しいと思います。*塾長の考えになりますが、ニュアンス的に to 与格と for 与格の対比に似ている様な気がします。 |
||
 |
 |