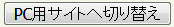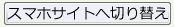英文読解から入試まで 完全マンツーマン指導
https://dictionary.cambridge.org/ja/dictionary/english/
塾長のコラム 2025年10月1日
 |
 |
|
関係詞1 |
||
2025年10月1日 皆様、KVC Tokyo 英語塾 塾長 藤野 健です。 少し前に分詞構文について解説しましたが、そこでは分詞構文が従属接続詞、等位接続詞、或いは非接続用法の関係詞(=関係代名詞、関係形容詞、関係副詞など)を利用しての書き換えが適宜可能である事を述べました。いずれも1つの文(主文)に対して、別の情報を加える、併記する用法ですが、考えて見ると少なくとも英語とは、ダラダラと何かの文言を付け加えるのが好きな一面のある言語であることが分かります。しかし、人間の脳の認知機能からは一つの発想に対してあれこれ付け加えるには理解の限度が有り、当然乍ら際限なく文言を加えて行くことは出来ません。<節度>が求められると言うことになります。分詞構文についても然りなのですが、複数の文章を<短縮して繋ぎ合わせる>と言葉の経済に資する上に、<何だか端整で知的な雰囲気も纏えて>カッコいい、の発想自体は特に悪いものではありませんが、1つの文にては単純な1つの事実のみを述べるのが矢張り本来のあるべき姿なのだろうと塾長は考えます。複数情報を繋ぎ合わせる際に、主文に対して、どの文言が付け加えの部分であるのかを示す標識、即ちマーカーの類いを接続詞と言うのですが、関係詞はその1つになります。 まぁ、文章同士をくっつけて<関係させる>際に利用される語のことを関係詞と呼称するのですが、広い意味での接続詞の仲間の1つになります。従属接続詞、等位接続詞を利用して付け加える文構造、即ち従属接続節、等位接続節(独立節とも言う)は、飽くまで主文全体に付加情報を与えるものであるのに対し、主文の中の特定の名詞や主文が主張する想念(これは1つのモノ扱いになります)をキメ打ちして追加情報を<貼り付ける>、強い或いは比較的強い接着剤の働きをするのが関係詞です。この意味で形容詞として機能するもの故、関係詞が構成する節、即ち関詞詞節 relative clauses は形容詞節と呼称出来ます。 モノの形容に関してですが、日本語ではモノの形容語句は名詞の前に置く一方、英語では極く短い文言は別として、長い構造は後置修飾させます。これ故、日本語で解釈するには返り点読みを余儀なくされ、特に初学者は頭を抱えるに至りますし、実際そのまま愚直に!訳したところで意味が取れないなどと却って苦情を言われてしまい兼ねません。この返り点読みを止めさせ、英文を語順のままに理解させるべく、巷ではスラッシュリーディング法が良い、同時通訳的者を倣え(これは当塾長の考え)などと主張されますが、要は、そのまま意味を頭に input しつつ英文を読み下すのが合理的だ、との指導法になりますね。 この様な英文解釈、リーディング上の技法面にも触れつつ、関係詞-関係代名詞、関係形容詞、関係副詞などが有ります-を文法面と意味用法面から含めてザッと一通り見て行きましょう。関係詞の構文上の理解は容易ゆえ、個々の用法や注意点を列挙する形がメインとなりますが、これまでの知識の整理がてら読み進めてみて下さい。損はしない筈です。その第1回目となります。 英国ケンブリッジ英語辞典並びに Collins 英語辞典の用例を主に参考に解説を加えて行きます。https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/whichhttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/whichhttps://en.wikipedia.org/wiki/English_relative_clauseshttps://en.wikipedia.org/wiki/Conjunction_(grammar)#Subordinating_conjunctionshttps://ja.wikipedia.org/wiki/関係詞https://en.wikipedia.org/wiki/Relativizer*これらに引用されている文献を参照すると更に詳細な学説が得られます。https://www.thoughtco.com/zero-relative-pronoun-1692623https://www.thoughtco.com/zero-or-bare-infinitive-1692621『試験に出る英文法』 森一郎、青春出版社、1971年 第4章 関係代名詞・関係副詞 pp.58-78『チャート式 英文解釈』 鈴木進、数研出版、昭和51年、第2編文の構造上よりの解釈 第3章2 形容詞節 pp.132-168『チャート式 英文法』 荒木良治、数研出版、昭和62年、第3章 5関係代名詞pp.103-11 第5章 3関係副詞 pp.164-168これらの基本的構成並びに(難解な)例文を幾つか参考にしていますが、塾長なりの視点から批判的検討を加え、また一部、より現代的な、或いはより正しい明確な表現となる様、書き換えたものも併記しています。『文法化する英語』 保坂道雄 開拓社 2024年第3刷 第6章 関係代名詞の文法化 |
||
 |
 |
関係代名詞を使う時ってネイティブの頭の中はどうなってる?直接質問攻めしてみた!
Kevin's English Room / 掛山ケビ志郎 2020/11/09
https://youtu.be/9g9Bafiz2dw
言語なるものは音符と同じで時系列に沿って発想し進むのみで、返り点で戻る性質のもの
ではありません。日本語では、<晴れた日に公園でおにぎりを食べている少女>、とカメラ
が遠景から入り、次いで対象にズームアップされ、最後に少女の顔にピントが合いますが、
英語では、この真逆になりますね。まず少女を捉え、それ以下は関係代名詞で叙述する事
になります。この<遠→近> vs.<近→遠>の発想法の本質的な違い-最初にどこにピン
トを合わすのか-は、漫画のコマ割などにも現れている様にも塾長は感じています。
 |
 |
|
関係詞とはなんですか?*関係詞 (Rlative, Rlativizer ) には大きく分けて関係代名詞、関係形容詞(正確には関係限定辞)、関係副詞の3つがあります。*おのおの、代名詞と接続詞を、形容詞(限定辞)+名詞と接続詞を、副詞と接続詞を、兼ね備えた働きを行い、2つの別個の文章を繋げて1つの文にする機能を持ちます。*より正確に言えば、関係詞の前に置かれている語(句や節:先行詞 Antecedent)に対して、後ろの節 (関係節と言う)を形容詞節として連結する機能を持つ語です。*日本語で言うと、取り敢えずは、あれ、それ、その、いつ、どこ、などと口にしておき、次いでその<中身>を追加して述べる様な表現形式になります。*日本語の文法品詞に英語と同じ機能を持つ、明確な形としての関係詞なるものは存在しません。*言語なるものは音符と同じで時系列に沿って発想し進み、返り点で戻る性質のものではありません。*荒木良治 『チャート式 英文解釈』 5 関係代名詞 (Relative Pronoun) の囲みコラムに、<日本語と英語の語順: 日本語の語順では「草の上で一踊っている 一女の子」と言う。映画で言えば、まずスク リ-ンに草原が映り、誰かが踊っているのが見え、近づいてみるとそれは女の子だと言うことになる。同じ事を英語では a girl-who is dancing on the grass と言う。これはまず女の子が映り、カメラが少し下がるとその女の子は踊っているのが判る。さらにカメラが下がるとそこは草原であることが判る。日本語は遠くから近くへ、英語は近くから遠くへである。>、とあります。(表記及び句読点を改変)*日本語ではカメラが遠景から入り、次いで対象にズームアップされ、最後に少女にピントが合いますが、英語では、この真逆になりますね。まず少女を捉え、それ以下は関係代名詞で叙述するスタイルになります。この<日: 遠→近> vs.<英: 近→遠>の発想法の本質的な違い-最初にどこにピントを合わすのか-は、漫画のコマ割などにも現れている様にも塾長は感じています。*この様な日英の発想法の違いの上に関係詞が存在していることを学校英語等でキッチリとまずは指導すべきですが、これに触れる教科書や学習参考書の類いを塾長は知りません。片手落ちの英語指導と言うべきでしょう。*日本語でも、「草の上で一踊っている (ところの)一女の子」と、<ところの>なる関係詞が存在し、それが通常は消えている、と考えられなくもありません。*実は、I Looked at a girl who was dancing on the grass. の文は、等位接続詞 and を用いて、I Looked at a girl and she was dancing on the grass.と述べても同意ですが、この<分離>スタイルは、関係詞が登場する以前の古英語のスタイルになります。cf.『文法化する英語』 保坂道雄 開拓社 2024年第3刷 第6章 関係代名詞の文法化*詰まりは叙述の時間軸通りに発想が進むことを明確に表していますが、この事実は、後の回にて扱う、制限用法 vs. 非制限用法の意味合いの考察の場で大きな意味を持って来ます。*I think that he is kind. の that は、<私はそれを思う、彼は親切だと。>とも解釈出来ますが、先行詞を失った様な関係代名詞と見倣すことも出来、その場合は空所型 (gap-type) 関係詞と分類される場合もあります。通常は、関係詞ではなく、接続詞、或いは節の始まりを示すマーカーとして理解されますが、関係代名詞的表現の成立を考察する上では何かのヒントを与えて呉れそうです。*以下、具体例に則して話を進めて行きます。*中高生が学校英語で習うレベルの極く基本的な内容も含みますが、知識の整理と復習がてらにザッと読み進めて下さい!関係代名詞 (Relative Pronoun)*閒係代名詞とは代名詞と接続詞を兼ねたようなものであり、前に置かれている語 (または句、節) を受けてその代名詞の役を果たすと同時に、それに続いている節 (=形容詞節) を先行詞に結びつける接続詞の役割も果します。*まぁ、文章の接着剤ですね。*関係代名詞の節と先行詞 (Antecedent) の構造:---------------------- 主部 -------------------The lady who was here yesterday is coming this afternoon.先行詞 関係代名詞の節=形容詞節 述語動詞昨日ここにいた婦人が午後に来ます。*この文では、who は lady を受けていると同時に、was here yesterday の主語となっています。そして who was here yesterda 全体が形容詞節として名詞 lady を修飾しています。*幾つかある関係代名詞のいずれを選択するかは、先行詞が人間かそれ以外の非人間かによって決まります。例えば、who 及びその派生語 (whose を除けば whom, whoever など)は、一般的に人間の先行詞に限定されますが、which および what とその派生語は、ほとんどの場合、動物或いは事物を指します。*whichや that には所有格が存在しないため、whose を用いますが、これは必然的に人間以外の先行詞にも使われます。*whose を使う代わりに of which などを使う事も出来ます。*関係代名詞の種類と格変化の概略を表にすると次のようになります:------------------------------------------------------------------格 主格 所有格 目的格先行詞人 who whose whom動物・物 which of which/ whose which人・物・動物 that that that先行詞+関係代名詞 what what what------------------------------------------------------------------*上の表のほかに but, as, than も 関係代名詞 (疑似関係代名詞)として用いられる場合があります。 |
||
 |
 |
WHO | WHOM | WHOSE | WHO'S - Important English Grammar Lesson!
English with Lucy 2022/05/20
https://www.youtube.com/watch?v=Kmxd_nej-wk
これらの語の疑問詞としての役目と関係代名詞としての役目について、良い例文を交えて
ルーシーさんが解説して呉れます。元々の疑問詞が関係代名詞としての機能を二次的に
派生させたのですが、2つは意味合いも用法上の決まり事も良く似ています。
 |
 |
|
各論who whose whom*who, whose, whom は人を指示する名詞句・名詞を先行詞として用いられます。*歴史的には、元々疑問詞として機能してきたものが関係代名詞としての機能を二次的に派生させたものです。*意味合い、用例上の決まりにも重なるところは多々あります。cf.『文法化する英語』 保坂道雄 開拓社 2024年第3刷 第6章 関係代名詞の文法化1. who*who は主格として機能し、関係代名詞の節の中の主語として用いられ、人称代名詞で言うと、I, we, you, he, she, they に相当します。.The man who wrote this novel is coming to the party.この小説を書いた人がパ -ティーに来ますよ。ここに who は先行詞 man を受けると同時に、関係代名詞節 who wrote this novel の中で主語となっています。*関係詞節の中の動詞 (V')と、主節の動詞 (V) を見分けることが構文理解のキモになります。註:海軍の艦船や船舶など、特定のモノは女性の代名詞で表現され、またペットやその他の動物は、その性別や(擬人化された)「人称」で扱われることが多いのですが、この様な場合は関係代名詞として who, whose, whom が用いられます。They have a dog, who always gives us a welcome.彼らは犬を1頭飼っているんですが、その犬はいつも我々を喜んで迎えて呉れます。2. whosewhose は who の所有格ですが、名詞の前に形容詞的に置かれます。人称代名詞で言えば my, our, your, his, her (所有格), their に相当します。There is a lady whose watch has been stolen.時計を盗まれた婦人がいます。*この文は There is a lady. Her watch has been stolen, の2文を、 her の代わりに whose を用いて連結したものになります。What was the name of that man whose wife is a famous novelist?有名な小説家を妻に持つあの男の名前は何だったかしら。3 whomwho の目的格で、人称代名詞の me, us, you, him, her, them に相当します。The man (whom) you saw at the dance wants to have a talk with you.あなたがダンスの時会った人があなたとお話がしたいと言っています。*whom の先行詞は manで、saw の目的語になっています。cf. see someone = to visit or meet someone 訪問する、会うI saw him yesterday. 昨日彼に会いました。*whom は通常の会話、特に formal ではない書き言葉では省略されるのが一般的です。*ただし、次の文の様に前置詞が前にある場合は、前置詞の目的語として機能していますので、whom は省略できません。The visitor for whom you were waiting has arrived.あなたが待っていた来客が到着しました。cf. wait for は物理的、動作的に待つ、の意味になります。*精神的に待ち望んでいた、を表したい場合は、The visitor you were expecting has arrived. などと述べます。 |
||
 |
 |