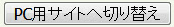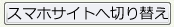英文読解から入試まで 完全マンツーマン指導
https://dictionary.cambridge.org/ja/dictionary/english/
塾長のコラム 2025年10月15日
 |
 |
|
関係詞4 |
||
2025年10月15日 皆様、KVC Tokyo 英語塾 塾長 藤野 健です。 少し前に分詞構文について解説しましたが、そこでは分詞構文が従属接続詞、等位接続詞、或いは非接続用法の関係詞(=関係代名詞、関係形容詞、関係副詞など)を利用しての書き換えが適宜可能である事を述べました。いずれも1つの文(主文)に対して、別の情報を加える、併記する用法ですが、考えて見ると少なくとも英語とは、ダラダラと何かの文言を付け加えるのが好きな一面のある言語であることが分かります。しかし、人間の脳の認知機能からは一つの発想に対してあれこれ付け加えるには理解の限度が有り、当然乍ら際限なく文言を加えて行くことは出来ません。<節度>が求められると言うことになります。分詞構文についても然りなのですが、複数の文章を<短縮して繋ぎ合わせる>と言葉の経済に資する上に、<何だか端整で知的な雰囲気も纏えて>カッコいい、の発想自体は特に悪いものではありませんが、1つの文にては単純な1つの事実のみを述べるのが矢張り本来のあるべき姿なのだろうと塾長は考えます。複数情報を繋ぎ合わせる際に、主文に対して、どの文言が付け加えの部分であるのかを示す標識、即ちマーカーの類いを接続詞と言うのですが、関係詞はその1つになります。 まぁ、文章同士をくっつけて<関係させる>際に利用される語のことを関係詞と呼称するのですが、広い意味での接続詞の仲間の1つになります。従属接続詞、等位接続詞を利用して付け加える文構造、即ち従属接続節、等位接続節(独立節とも言う)は、飽くまで主文全体に付加情報を与えるものであるのに対し、主文の中の特定の名詞や主文が主張する想念(これは1つのモノ扱いになります)をキメ打ちして追加情報を<貼り付ける>、強い或いは比較的強い接着剤の働きをするのが関係詞です。この意味で形容詞として機能するもの故、関係詞が構成する節、即ち関詞詞節 relative clauses は形容詞節と呼称出来ます。 モノの形容に関してですが、日本語ではモノの形容語句は名詞の前に置く一方、英語では極く短い文言は別として、長い構造は後置修飾させます。これ故、日本語で解釈するには返り点読みを余儀なくされ、特に初学者は頭を抱えるに至りますし、実際そのまま愚直に!訳したところで意味が取れないなどと却って苦情を言われてしまい兼ねません。この返り点読みを止めさせ、英文を語順のままに理解させるべく、巷ではスラッシュリーディング法が良い、同時通訳的者を倣え(これは当塾長の考え)などと主張されますが、要は、そのまま意味を頭に input しつつ英文を読み下すのが合理的だ、との指導法になりますね。 この様な英文解釈、リーディング上の技法面にも触れつつ、関係詞-関係代名詞、関係形容詞、関係副詞などが有ります-を文法面と意味用法面から含めてザッと一通り見て行きましょう。関係詞の構文上の理解は容易ゆえ、個々の用法や注意点を列挙する形がメインとなりますが、これまでの知識の整理がてら読み進めてみて下さい。損はしない筈です。その第4回目となります。 英国ケンブリッジ英語辞典並びに Collins 英語辞典の用例を主に参考に解説を加えて行きます。https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/whichhttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/whichhttps://en.wikipedia.org/wiki/English_relative_clauseshttps://en.wikipedia.org/wiki/Conjunction_(grammar)#Subordinating_conjunctionshttps://ja.wikipedia.org/wiki/関係詞https://en.wikipedia.org/wiki/Relativizer*これらに引用されている文献を参照すると更に詳細な学説が得られます。https://www.thoughtco.com/zero-relative-pronoun-1692623https://www.thoughtco.com/zero-or-bare-infinitive-1692621『試験に出る英文法』 森一郎、青春出版社、1971年 第4章 関係代名詞・関係副詞 pp.58-78『チャート式 英文解釈』 鈴木進、数研出版、昭和51年、第2編文の構造上よりの解釈 第3章2 形容詞節 pp.132-168『チャート式 英文法』 荒木良治、数研出版、昭和62年、第3章 5関係代名詞pp.103-11 第5章 3関係副詞 pp.164-168これらの基本的構成並びに(難解な)例文を幾つか参考にしていますが、塾長なりの視点から批判的検討を加え、また一部、より現代的な、或いはより正しい明確な表現となる様、書き換えたものも併記しています。 |
||
 |
 |
RELATIVE CLAUSES with Who / Whom / Which / That. PART 1
Easy Grammar Explanation of relative clauses English Speaking 360 2024/10/18
https://www.youtube.com/watch?v=sZvZftDVWEw
4:12 A lawyer represented us in court. + The lawyer specializes in labor law.
→ A lawyer who specializes in labor law represented us in court.
一人の弁護士が法廷で私たちを代表した。+ その弁護士は労働法を専門としている。
→ 労働法を専門とする一人の弁護士が法廷で私たちを代表した。
制限用法で先行詞を限定することで意味が明確に絞り込まれ、或る1人の弁護士の素性が
明らかにされ、特定 identify されました。この記述はそれ以上それ以下では無く、<別の
専門の弁護士が我々を代表しました。>などは特に含意しません。仮に言外に別の存在を
匂わす曖昧性を持ち込むのであれば、そもそも制限(=限定)用法で記述する精神に矛盾し
てしまいます。この様な、明確性の高い2つの文の組み合わせのみが関係代名詞の制限
用法に基本的且つ単純明快に使用されていることにご注意下さい。
 |
 |
|
2つの単文と関係代名詞構文との関係1*次回及び次々回コラムにて、制限用法 vs, 非制限用法について詳細に分析、解説しますが、今回はその前哨戦としての位置づけです。*さて、関係代名詞の構文は2つの単文に分割し得、またその逆を行う事も出来ます。The lady who was here yesterday is coming this afternoon.この文を2つの単文に置換すると、→The lady was here yesterday. + She is coming this afternoon.その夫人は昨日ここにいた。 彼女は午後遣って来ます。*この逆に、形式上は2つの単文を関係代名詞を用いて1つの複文にすることも出来ます。*この様な操作は、関係詞の制限用法の意味するところの本質を解明することのみならず、制限用法と非制限用法の持つ意味合いの違いを鮮明にすることにも繋がります。--------------------------------------------1. I will employ a man. He speaks French well.私は或る男性を雇うつもりだ。彼はフランス語を流暢に話す。→ 合成すると2. I will employ a man who speaks French well.私はフランス語を上手に話す男を一人雇う積もりだ。.*これは、含意としては、雇う積もりの1人の男がどう言う者であるのかを、定義、名札付けして他から区別する意味になります。*上記 1の場合、a man は不特定な1人ではなく、話し手のアタマの中では既に特定の1名を思い浮かべています。*一方、2での a man は、1人の特定の男を思い浮かべ、その当人に付いての説明を加える記述をしているとも解釈可能ですし、また、より一般化した1人の男としての定義づけの意味としても理解可能です。*2を後者の視点で考えると、以下の例の様に更に別の属性の人間を雇う可能性もあれば、この当人のみしか雇わない可能性などもあるのですが、文章としては文字列以上の事は表現しません。I will also employ another man who speaks German well.私はドイツ語をよく話す別の人間も採用するつもりだ。I have no intention of hiring anyone else besides this person.私は彼以外に人を雇う積もりは無い。cf. × I will employ a man, who speaks French well. この非制限用法は不文です。◯ I will employ Tom, who speaks French well.= I will employ Tom, because he speaks French well.私はトムを雇う積もりです。と言うのは彼はフランス語が得意だからです。この文なら成立します。*と言いますか、最初から適切な接続詞を用いて明確に記述すれば済む話です。 |
||
 |
 |
Non-defining relative clauses | English grammar rules
Crown Academy of English 2016/03/21
https://www.youtube.com/watch?v=_B8BRYoJJ6M
2:00 We visited Hyde Park, which is close to Buckingham Palace.
ハイドパークはロンドンに1つしか無く、<定義して他から区別する>必要は無いので
制限用法にはしない旨の説明がなされます。即ち制限用法とは、先行詞を修飾して
他とは異なる別個のものであると、<切り離し明示する>意味があると云う訳です。
 |
 |
|
ここに、cf. a person/ thing = only one person/ thingcf. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/aA or an is the indefinite article. It is used at the beginning of noun groups which refer to only one person or thing. The form an is used in front of words that begin with vowel sounds.不定冠詞は「a」または「an」です。これは、唯一の人物や物事を指す名詞句の先頭に置かれます。母音で始まる単語の前では「an」の形が使われます。*1人の男=たった1人の男、ですね。3. I have a son. He speaks French well.私には息子が一人だけいます。彼はフランス語を流暢に話します。→ 合成すると4. I have a son who speaks French well.私にはフランス語を流暢に話す息子が一人います。=息子は1人だけ居て、彼はフランス語を話すんです。(説明的記述)=フランス語を流暢に話すという属性を抱えた息子が一人、います。(定義づけ、限定)*制限用法の説明的記述 vs. 限定定義付け、に関しては、次回、関係詞5 をご参照下さい。*後ろの解釈では、一人息子なのか他にも息子がいるのかについては単に言及しません。即ち、可能性は有るものの、言外に他の息子が居るかどうかについては別段示唆しません。*即ち3→4に書き換える過程で、3に於いて明示されて居た<息子は1人しか居ない>の情報が失われ、意味が曖昧化しています。*関係詞を用いたこの文に対しては少なくとも以下の2通りの解釈が成立し得るでしょう。I have a son who fluently speaks French, but he is my only son.私にはフランス語を流暢に話す息子が一人いますが、息子は彼だけです。I have another son who speaks German well.私にはドイツ語を流暢に話す別の息子がいます。*多義性を持ち得る可能性のある関係代名詞構文は用いずに、別の表現-複数個の単文-で明確に記述した方が良さそうです。*分詞構文の場合と同じく、短くコンパクトにする分、情報が抜け落ちる危険性もある訳です。即ち、I have three sons who fluently speak French私には息子が3人居て皆フランス語を上手に話します。私にはフランス語を流暢に話す息子が3人います。などと両意に取れる曖昧な記述はせずに、I have three sons who fluently speak French and one son who does not speak French at all.私にはフランス語を流暢に話す息子が3人と、全くフランス語を話さない息子が1人います。I have three sons. Only one of them speaks French fluently.私には息子が3人います。その内の1人だけがフランス語を流暢に話します。I have three sons. All of them speak French fluently.私には息子が3人います。その全員がフランス語を流暢に話します。などの様に最初から明確な記述を行えばそれで済むだけです。*<合成>時に意味の違いが生じ得る可能性を指導するのが学校英語教育に必要だろうと塾長は強く思いますね。*意味の曖昧で寸足らずな関係代名詞表現を用いて、<言外に別の兄弟がいることを(確実に)匂わせる表現だ>などと、本邦の英語教員や塾講師などが鬼の首でも取ったが如くに騒ぎ立てますが、そもそも曖昧な英文は排除して明確性の高い表記を行う様に生徒に求めれば良いだけの話になります。*言外のニュアンスを読め、などと英文の曖昧性を許容し、それが英文読解の極意であるなどと旧態依然たる<文学性優先、卑屈英語>の奇矯な英語指導を行っている様では、個人の明確な意思を相手に誤解無く伝えんとの言語の第一義的意義を spoil することになります。*だから何年学校英語の指導を受けても自らの意思を相手に明確に伝えること、即ち会話、英作が出来ないのでしょう。*英語には万人に対する明確性を第一ものとして考える立場-例えば学術英語-の世界が拓けていることを学校英語時代に指導すべきでしょうね。*本邦英語教員の出自を鑑みるに、一言一句の意味の付き詰めが要される論文執筆の経験無く、現状では厳しいだろうとは思いますが。 |
||
 |
 |