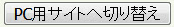英文読解から入試まで 完全マンツーマン指導
https://dictionary.cambridge.org/ja/dictionary/english/
塾長のコラム 2025年10月25日
 |
 |
|
関係詞6 |
||
2025年10月25日 皆様、KVC Tokyo 英語塾 塾長 藤野 健です。 少し前に分詞構文について解説しましたが、そこでは分詞構文が従属接続詞、等位接続詞、或いは非接続用法の関係詞(=関係代名詞、関係形容詞、関係副詞など)を利用しての書き換えが適宜可能である事を述べました。いずれも1つの文(主文)に対して、別の情報を加える、併記する用法ですが、考えて見ると少なくとも英語とは、ダラダラと何かの文言を付け加えるのが好きな一面のある言語であることが分かります。しかし、人間の脳の認知機能からは一つの発想に対してあれこれ付け加えるには理解の限度が有り、当然乍ら際限なく文言を加えて行くことは出来ません。<節度>が求められると言うことになります。分詞構文についても然りなのですが、複数の文章を<短縮して繋ぎ合わせる>と言葉の経済に資する上に、<何だか端整で知的な雰囲気も纏えて>カッコいい、の発想自体は特に悪いものではありませんが、1つの文にては単純な1つの事実のみを述べるのが矢張り本来のあるべき姿なのだろうと塾長は考えます。複数情報を繋ぎ合わせる際に、主文に対して、どの文言が付け加えの部分であるのかを示す標識、即ちマーカーの類いを接続詞と言うのですが、関係詞はその1つになります。 まぁ、文章同士をくっつけて<関係させる>際に利用される語のことを関係詞と呼称するのですが、広い意味での接続詞の仲間の1つになります。従属接続詞、等位接続詞を利用して付け加える文構造、即ち従属接続節、等位接続節(独立節とも言う)は、飽くまで主文全体に付加情報を与えるものであるのに対し、主文の中の特定の名詞や主文が主張する想念(これは1つのモノ扱いになります)をキメ打ちして追加情報を<貼り付ける>、強い或いは比較的強い接着剤の働きをするのが関係詞です。この意味で形容詞として機能するもの故、関係詞が構成する節、即ち関詞詞節 relative clauses は形容詞節と呼称出来ます。 モノの形容に関してですが、日本語ではモノの形容語句は名詞の前に置く一方、英語では極く短い文言は別として、長い構造は後置修飾させます。これ故、日本語で解釈するには返り点読みを余儀なくされ、特に初学者は頭を抱えるに至りますし、実際そのまま愚直に!訳したところで意味が取れないなどと却って苦情を言われてしまい兼ねません。この返り点読みを止めさせ、英文を語順のままに理解させるべく、巷ではスラッシュリーディング法が良い、同時通訳的者を倣え(これは当塾長の考え)などと主張されますが、要は、そのまま意味を頭に input しつつ英文を読み下すのが合理的だ、との指導法になりますね。 この様な英文解釈、リーディング上の技法面にも触れつつ、関係詞-関係代名詞、関係形容詞、関係副詞などが有ります-を文法面と意味用法面から含めてザッと一通り見て行きましょう。関係詞の構文上の理解は容易ゆえ、個々の用法や注意点を列挙する形がメインとなりますが、これまでの知識の整理がてら読み進めてみて下さい。損はしない筈です。その第6回目となります。 英国ケンブリッジ英語辞典並びに Collins 英語辞典の用例を主に参考に解説を加えて行きます。https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/whichhttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/whichhttps://en.wikipedia.org/wiki/English_relative_clauseshttps://en.wikipedia.org/wiki/Conjunction_(grammar)#Subordinating_conjunctionshttps://ja.wikipedia.org/wiki/関係詞https://en.wikipedia.org/wiki/Relativizer*これらに引用されている文献を参照すると更に詳細な学説が得られます。https://www.thoughtco.com/zero-relative-pronoun-1692623https://www.thoughtco.com/zero-or-bare-infinitive-1692621『試験に出る英文法』 森一郎、青春出版社、1971年 第4章 関係代名詞・関係副詞 pp.58-78『チャート式 英文解釈』 鈴木進、数研出版、昭和51年、第2編文の構造上よりの解釈 第3章2 形容詞節 pp.132-168『チャート式 英文法』 荒木良治、数研出版、昭和62年、第3章 5関係代名詞pp.103-11 第5章 3関係副詞 pp.164-168これらの基本的構成並びに(難解な)例文を幾つか参考にしていますが、塾長なりの視点から批判的検討を加え、また一部、より現代的な、或いはより正しい明確な表現となる様、書き換えたものも併記しています。中尾俊夫・児馬修 編著 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館書店 1990年https://core.ac.uk/download/229256531.pdf『固有名詞を先行詞とする非制限的関係詞節とコンマについて』 マユー あき、人間と文化 207 ~ 213 (2017) 島根県立大学学術機関リポジトリ*無料で全文読めます。https://www.elec.or.jp/elecbulletin/7098https://www.elec.or.jp/wp-content/uploads/2024/07/img_bulletin_no033.pdf中島文雄 (1971)「Relative Clauseの分類」 『英語展望』 33,25-28, ELEC*無料で全文が読めます。*ELEC: 日本英語教育協議会https://www.elec.or.jp/ |
||
 |
 |
https://www.youtube.com/watch?v=a_mFlafGyy8
Defining and Non-Defining Relative Clauses - English Grammar Lesson
Oxford English Now 2019/07/26
制限用法と非制限用法の違いを復習がてらまたザッと確認して下さい。
that と why は非制限用法は有りません。共に前置詞は関係節の末に付
け加えますが、formal な場合は関係代名詞の前に前置詞を配置します。
that の前には前置詞は置けません。
 |
 |
|
制限用法 (Restrictive Use) と 非制限用法 (Nonrestrictive Use)*関係節 (関係代名詞節、関係形容詞節、関係副詞節) は、制限的関係詞節(制限節、restrictive clause, defining clause) と非制限節 (non-restrictiveclause, noon-defining clause) とに分類可能です。*構文表現上はコンマの有無以外に何ら違いはありません。*以下ここでは、関係代名詞についてのみ考察しますが、基本的な考え方は、関係形容詞、関係副詞にも当てはまります。*関係代名詞にて非制限用法が取れるのは who, whose, whom, which に限られ, that は非制限用法は取れません。*制限節は、主節からコンマで区切られず、主節の先行詞について本質的な情報を追加して他から区別する(即ち定義する define / 名札付けする identify する)為の用法であるのに対し、コンマで主節から区切られる非制限節は、先行詞の追加情報を付加するとされます。*この様に毎度説明はされるものの、本質的な情報か付け足しの情報かは、実は語り手側の判断です。第三者的には、制限用法であろうが省略しても文は成立しますし、本質的な判断は不可能です。*全ての言語同様に、英文は前から後ろへと文字の記述される順番に理解され、返り点で元に戻って先行詞に文言が掛かるとの言語ではありません。*従って、先行詞が提示され、その属性が更に絞り込まれ先鋭化するのであれば制限用法と文脈から理解し、先行詞の属性が絞り込まれずに別の枝が付け加わるのであれば非制限用法と、こちらも文脈で理解するだけのことになります。*形の上のコンマの有無よりも文脈で読み進めることが肝心カナメに感じますね。*この様な観点から、塾長はコンマの有無に捕らわれずに<適宜>文意を理解して進めるのが良い、と生徒達に指導しています。*実際のところ、コンマが無いものの非制限用法として解釈する方が通りが良い英文は数多く見ます。*非制限用法はコンマで表記することからお分かりの様に、元来書き言葉で利用されますが、口語でもコンマの箇所にワンクッションを置くなどのイントネーションを通しての工夫で、非制限的な、挿入句的な用法であることを示すことは或る程度は可能です。*尤も、単にコンマの有無の違いだけではなく、2つの間には意味論的な違いが存在するのは確かです。*以下、ここでは関係詞の内の関係代名詞に関して解説を進めます。 |
||
 |
 |
https://www.youtube.com/watch?v=apBUEsF7mrw
関係詞節の間違いはやめよう![Which & That] mmmEnglish 2019/07/19
こちらも上の動画と同じ立場の指導方ですね。最後にいずれが正しいかを問う
例文では native でも断言出来ないものも登場しますが、その場合は文脈依存
で制限か制限かを問うものになりますね。
 |
 |
|
制限用法と非制限用法との意味合いの違い*下記の幾つかの例でお分かりの様に、各例各々に別の次元でのニュアンスの違いを含意しています。*拘り出すと込み入った展開になりますが、基本は先行詞をガッチリと規定しているのか、ざっくばらんにあとから説明を付け足すのか、の違いです。------------------------------------------------------------------------------制限用法*中島文雄氏(当時津田塾大学教授)は、以下、 (1971)「Relative Clauseの分類」『英語展望』 33, 25-28, ELEC にて、https://www.elec.or.jp/wp-content/uploads/2024/07/img_bulletin_no033.pdf単なる制限用法 vs. 非制限用法の2項的対立に留まらず、関係節を意味論的から以下の様に更に細分しています:(以下引用)********************************************「関係詞節は,制限的 (restrictive) と非制限的 (non-restrictive) の2 種類にわけられるのが普通であるが、意味の上からいっても統語法の上からいっても 、次の 4種類にわける方が適当であると考えられる。すなわちI. Restrictive (制限的)II. Descriptive (記述的)III. Appositive (同格的)IV. Continuative (連続的)ひとつずつ例文をあげると、(1) Any book which is about linguistics is interesting.(2) I bought a book which was about linguistics.(3) This book, which is about linguistics, is interesting.(4) I bought a book today, which I will give to you later.(1) は、言語学に関する本はどれでもという意味であるから、any は book だけの Determiner ではなく、book which is about linguistics 全体にかかるものである。従って which 以下の関係詞節は book の意味を制限している。すなわち Restrictive relative clause である。これに反して(2)の関係詞節はbook を制限するというよりは、むしろ a book の説明、記述をしていると考えられる。それでこれを Descriptive relative clause として(1)から区別する。(3) はいわゆる Non-restrictiveの関係節であるが、(2) と同 じように記述的なはたらきをしている。ただしこの場合は、(2) のように a book に対 し修飾語的な関係ではなく、挿入文的な関係にある。それでこれを Appositive relative clause とよぶことにする。(4) の関係詞節は、 (3) の挿入文と似ているが、これは I bought a book. に対し、本来は独立文であるものが、関係詞を用いることによって、従属的に表現されたと解される。それでこれを Continuative relative clauseとよぶ。」********************************************と、いわゆる制限用法、非制限用法を各々2つに細分化して説明しています。ここに、(2) I bought a book which was about linguistics.≒ I bought a book, which was about linguistics. であり、<私は1冊の本を持って居て、それは言語学についての本です。>と解釈され、[<私は言語学についての本を持って居ます。>+<或いは別の本を持って居る可能性>]の解釈にはなりません。同様に、She has two brothers who work in this factory.彼女にはこの工場で働いている兄弟が2人いる。この文が記述的であるとすれば、分解すると、= She has two brothers. + They work in this factory. となります。*話し手の頭には、2人の兄弟のことがまず特定され、彼らについての説明、記述が為されているとも考えられますので、確かに中島氏の言う、Descriptive とも言えます。即ちこの文はShe has two brothers, who work in this factory. に意味的に非常に接近しており、制限用法と非制限用法の間にある存在と言う事が出来るでしょう。一方、限定的であると解釈すれば、[(正に)この工場で働いている兄弟が(兎に角)2人いる。]、と他から区別、明言していることから、他に兄弟がいる可能性もありますし、いない場合もあり得ます。*いずれに解釈するかは、文脈に依存し、論理的な意味合いに於いては曖昧性を排除出来ません。一方、The train that left Yokohama at 3:00 arrived here about 20 minutes late.横浜を3時に出た列車は約20分遅れてここへ到着した。(その列車はそれ1つであると確定しています)この文では、that 以下は先行詞を後ろから強固に特定するものゆえ、Restrictive と言えそうです。*この様に、制限用法であると<分類>しても、実際には内部で更に意味合いの違いが存在し得ることが理解出来るでしょう。 |
||
 |
 |
https://www.youtube.com/watch?v=_B8BRYoJJ6M
Non-defining relative clauses | English grammar rules
Crown Academy of English 2016/03/21
非制限用法メインにザッと解説して呉れます。
 |
 |
|
非制限用法She has two brothers, who work in this factory.彼女には兄弟が2人いるが, その2人はこの工場で働いている.)[「彼女には兄弟が2人しかいない」と断定的に述べてから、その兄弟に関する説明を付け加えています。〕*彼女には兄弟が2人しかいないことは確定しています。*前々回並びに前回コラムコラムにて触れましたが、動詞 haveから派生する特殊なニュアンスでもあると言えるでしょう。*非制限用法の関係代名詞の節は、「適当な接続詞+代名詞」を用いて書き換えが可能です。*分詞構文の分詞側が適当な接続詞を用いて書き換え可能な点とよく似ています。*要は、非制限用法とは、含みを持たせた多義性を抱える、文学的な表現だと言う話になりますね。I met a man, who told me the news.=…, and he told…私はひとりの男に会ったが、その男がそのニュ-スを伝えてくれました。*この and は時間差を表す and ですね。*中島氏に従えば、接続詞で繋ぐ、時間差を伴う連続用法になります。I wished to marry her, which proved to be impossible.私は彼女と結婚したかった。しかし,それは不可能であることがわかりました。= I wished to marry her, but that proved to be impossible.(同じく連続用法)The two boys, who did not suffer from sea sickness, paid no heed to the raging waves. =…, because they did not suffer…その2人の少年は船酔いをしなかったので荒波を少しも気にしませんでした。I cannot read this book, which is so difficult.私はこの本を読むことができません。というのはそれは非常にむずかしいからです。= I cannot read this book, because it is so difficult.The woman, who was very poor, never complained about her lot. = though she was very poor,…その婦人は大変貧しかったけれど、少しも自分の運命の不服を口にしませんでした。The old man, who is poor, is quite contented.その老人は,貧しいけれども、まったく満足しています。= The old man, though he is poor, is quite contented.The London train, which should arrive at 5:30, is late.ロンドン行きのその列車は、5 時半に着くはずですが、遅れています。*中島氏に従えば、同格的用法。*一般的には、コンマの有無も含め、話し手が意味したいだろうと想像される文脈に沿い、制限用法として解釈するのか、非制限用法として解釈すべきなのかの揺らぎが大きく出てしまいますが、これは避けることが出来ません。*以下、2つの用法並びに各例文に於ける意味合いの違いを比較して下さい:非制限用法The builder, who erects very fine houses, will make a large profit. (non-restrictive)その建設業者は、もし非常に立派な家を建てるなら、大きな利益を上げるでしょう。= The builder, if / when he erects very fine houses, will make a large profit. (non-restrictive)*the builder は話し手が知っている特定個人を指します。制限用法The builder who erects very fine houses will make a large profit. (restrictive)とても立派な家を建てる建設業者は、大きな利益を上げるでしょう。*the builder は一般的な建築業者を表している。*立派な家を建てない建築業者も存在する可能性はあり得る。= (一般的に)「とても立派な」家を建てる業者こそが大きな利益を上げる。= Generally speaking, it is the builders who construct truly magnificent homes that will reap the greatest profits.制限用法The ring that my grandma gave me is worth a lot of money.おばあちゃんが私に呉れたその指輪はとても高価なのよ。(常識のセンで、女性は複数の指輪を持って居てその数あるリングの内の1つを指している)非制限用法The ring, which my grandma gave me, is worth a lot of money.その指輪は、おばあちゃんが私に呉れたんだけど、とても高価なのよ。制限用法Food that is cooked with soy oil can give him an alleregicreaction.(一般的な話として)大豆油で調理された(=第三者に拠り調理されて市販/提供される)食品は、彼にアレルギー反応を引き起こす可能性があります。非制限用法Food, which is cooked with soy oil, can give him an alleregic reaction.食品は、大豆油で調理される(=購入後に自分で調理する)と、彼にアレルギー反応を引き起こす可能性があります。= When cooked with soy oil, food can cause an allergic reaction to him.*上の2文の意味には実際のところ殆ど違いはありません。 |
||
 |
 |