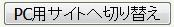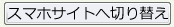英文読解から入試まで 完全マンツーマン指導
https://dictionary.cambridge.org/ja/dictionary/english/
塾長のコラム 2025年11月1日
 |
 |
|
関係詞7 |
||
2025年11月1日 皆様、KVC Tokyo 英語塾 塾長 藤野 健です。 少し前に分詞構文について解説しましたが、そこでは分詞構文が従属接続詞、等位接続詞、或いは非接続用法の関係詞(=関係代名詞、関係形容詞、関係副詞など)を利用しての書き換えが適宜可能である事を述べました。いずれも1つの文(主文)に対して、別の情報を加える、併記する用法ですが、考えて見ると少なくとも英語とは、ダラダラと何かの文言を付け加えるのが好きな一面のある言語であることが分かります。しかし、人間の脳の認知機能からは一つの発想に対してあれこれ付け加えるには理解の限度が有り、当然乍ら際限なく文言を加えて行くことは出来ません。<節度>が求められると言うことになります。分詞構文についても然りなのですが、複数の文章を<短縮して繋ぎ合わせる>と言葉の経済に資する上に、<何だか端整で知的な雰囲気も纏えて>カッコいい、の発想自体は特に悪いものではありませんが、1つの文にては単純な1つの事実のみを述べるのが矢張り本来のあるべき姿なのだろうと塾長は考えます。複数情報を繋ぎ合わせる際に、主文に対して、どの文言が付け加えの部分であるのかを示す標識、即ちマーカーの類いを接続詞と言うのですが、関係詞はその1つになります。 まぁ、文章同士をくっつけて<関係させる>際に利用される語のことを関係詞と呼称するのですが、広い意味での接続詞の仲間の1つになります。従属接続詞、等位接続詞を利用して付け加える文構造、即ち従属接続節、等位接続節(独立節とも言う)は、飽くまで主文全体に付加情報を与えるものであるのに対し、主文の中の特定の名詞や主文が主張する想念(これは1つのモノ扱いになります)をキメ打ちして追加情報を<貼り付ける>、強い或いは比較的強い接着剤の働きをするのが関係詞です。この意味で形容詞として機能するもの故、関係詞が構成する節、即ち関詞詞節 relative clauses は形容詞節と呼称出来ます。 モノの形容に関してですが、日本語ではモノの形容語句は名詞の前に置く一方、英語では極く短い文言は別として、長い構造は後置修飾させます。これ故、日本語で解釈するには返り点読みを余儀なくされ、特に初学者は頭を抱えるに至りますし、実際そのまま愚直に!訳したところで意味が取れないなどと却って苦情を言われてしまい兼ねません。この返り点読みを止めさせ、英文を語順のままに理解させるべく、巷ではスラッシュリーディング法が良い、同時通訳的者を倣え(これは当塾長の考え)などと主張されますが、要は、そのまま意味を頭に input しつつ英文を読み下すのが合理的だ、との指導法になりますね。 この様な英文解釈、リーディング上の技法面にも触れつつ、関係詞-関係代名詞、関係形容詞、関係副詞などが有ります-を文法面と意味用法面から含めてザッと一通り見て行きましょう。関係詞の構文上の理解は容易ゆえ、個々の用法や注意点を列挙する形がメインとなりますが、これまでの知識の整理がてら読み進めてみて下さい。損はしない筈です。その第7回目となります。 英国ケンブリッジ英語辞典並びに Collins 英語辞典の用例を主に参考に解説を加えて行きます。https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/whichhttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/whichhttps://en.wikipedia.org/wiki/English_relative_clauseshttps://en.wikipedia.org/wiki/Conjunction_(grammar)#Subordinating_conjunctionshttps://ja.wikipedia.org/wiki/関係詞https://en.wikipedia.org/wiki/Relativizer*これらに引用されている文献を参照すると更に詳細な学説が得られます。https://www.thoughtco.com/zero-relative-pronoun-1692623https://www.thoughtco.com/zero-or-bare-infinitive-1692621『試験に出る英文法』 森一郎、青春出版社、1971年 第4章 関係代名詞・関係副詞 pp.58-78『チャート式 英文解釈』 鈴木進、数研出版、昭和51年、第2編文の構造上よりの解釈 第3章2 形容詞節 pp.132-168『チャート式 英文法』 荒木良治、数研出版、昭和62年、第3章 5関係代名詞pp.103-11 第5章 3関係副詞 pp.164-168これらの基本的構成並びに(難解な)例文を幾つか参考にしていますが、塾長なりの視点から批判的検討を加え、また一部、より現代的な、或いはより正しい明確な表現となる様、書き換えたものも併記しています。中尾俊夫・児馬修 編著 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館書店 1990年https://core.ac.uk/download/229256531.pdf『固有名詞を先行詞とする非制限的関係詞節とコンマについて』 マユー あき、人間と文化 207 ~ 213 (2017) 島根県立大学学術機関リポジトリ*無料で全文読めます。https://www.elec.or.jp/elecbulletin/7098https://www.elec.or.jp/wp-content/uploads/2024/07/img_bulletin_no033.pdf中島文雄 (1971)「Relative Clauseの分類」 『英語展望』 33,25-28, ELEC*無料で全文読めます。*ELEC: 日本英語教育協議会https://www.elec.or.jp/ |
||
 |
 |
https://www.youtube.com/watch?v=toHuxDBmteM
WHICH vs THAT | What's the difference? | Learn with examples
Learn Easy English 2020/04/08
非制限用法には which を、一方、制限用法には that を用いるとの
割り切り方の指導法ですが、簡潔明快な利点は認めざるを得ません。
この規定的な「ルール」は1851年にグールド・ブラウンによって提案さ
れたものですが、 1926年にはH.W.ファウラーによって支持されました。
 |
 |
|
真の意味での制限用法では無い記述*制限用法の形を取っていても、実は先行詞を規定、制限していない場合も見られます。*実際には非制限的な意味合いで利用されていると言う訳です。完全な意味での制限節ではありません。*前回のコラムで、制限用法とされるものの、先行詞を強力に定義するものではなく、先行詞に対して情報を付け加えるものを、<記述的>制限用法として紹介しました。*これは、コンマを添えても意味に殆ど変わりがなく、だったら最初からコンマを付けて記述すべきものでもあります。*即ち、真の意味での制限用法では無い例と言えるでしょう。換言すると、*コンマが打たれていないが故の制限用法と言っても、先行詞に対する記述説明的な情報を付加する場合には、<コンマを打ち忘れた非制限用法>と理解して読み下すのが正しい場合は実際多いです。*この様なケースでは、実際、非制限用法として訳しても意味合いに於いて違いが生じません。*即ち、コンマがあるものとして意味を解釈した場合とコンマが無い場合との間で意味合いに大差がなければ、事実上の非制限用法と考え、コンマを加えるべきでしょう。The father who had planned my life to the point of my unsought arrival in Brighton took it for granted that in the last three weeks of his legal guardianship I would still act as he directed. He sounded like the clergyman [that] he was.」私がブライトンに到着するまでの間に私の人生を計画していた当の父親は、彼の法定後見人としての最後の3週間も、私が彼の指示通りに行動することを当然だと考えていた。彼は実際まるで聖職者の様だった。cf. the clergyman [that] he was 実際そうであるところの聖職者= the clergyman that was indeed suchcf. to the point of my arrival = to the time/ moment of my arrival = just before my arrivalここに、The father who had planned my life to the point of my unsought arrival in Brightonの who 以下は、[主語 the father を他から区別する為の制限用法としての記述であり、従って<そうしなかった別の父親も存在する可能性がある>]との論理を示し得ますが、実際には the father はその当人1人であることが常識のセンから疑義を生じません。従って厳密な意味での制限用法ではなく、コンマで前後を括っても同意となるものです。*そもそもこの文を目にして、別の父親が居たなどと<妄想>する者は一人もいない筈ですね。→The father, who had planned my life to the point of my unsought arrival in Brighton, took it for granted that in the last three weeks of his legal guardianship I would still act as he directed. He sounded like the clergyman [that] he was.当の父は、私がブライトンに到着するギリギリまで私の人生を計画していて呉れていたのだが、彼の法定後見人としての最後の3週間、私が彼の指示通りに行動することを当然だと考えていた。彼の言葉はまるで聖職者の様だった*コンマを使うこの記述が正確でしょう。*この英文に於いて、なぜ、コンマが使用されていないのかについて、マユー あき氏 (2017) は、「先行詞 the father 自体が持つ情報よりも関係詞節が伝える情報の重要度が高く、伝達の中心と意識されたと考えられる。関係詞節で表される内容は主節の内容を解釈する際に必要な背景的理由にあたる情報を提供しているという点でもその情報の重要度は高くなる。その結果、コンマ無しで関係詞節が先行詞と一体化しているのであろう。」と考察しています。*<単なる情報の追加であればコンマを打つべきところ、単なる情報以上のものであるので、コンマを使わなかった>との解釈ですね。塾長が選んだ別例:*以下の3文は、関係詞2にて一度説明を加えていますが、ここに再掲します。On our way to the Tower of London, we passed a tall pillar which stands where the Great Fire of London broke out in 1666.ロンドン塔へ行く途中、我々は 1666年のロンドン大火が起こった地点に立っている高い記念柱の傍を通り過ぎました。*which 以下は先行詞を追加説明するものですので、<, which>と見做し、分割して和訳しても同値です。= ロンドン塔へ行く途中、我々は一本の高い記念柱の傍を通り過ぎましたが、それは1666年のロンドン大火が起きた場所に立っていました。*コンマを付けずに限定性の強い意味合いだと解釈すると、まさしく1666年のロンドン大火が起こった地点だったのだ、の意味に読めます。The band played a familiar tune which had everyone clapping along.バンドが馴染み深い曲を演奏すると、皆が手拍子を打ち始めました。*the tune have everyone clapping along これはSVOC の使役表現です。*まず曲が演奏され、時間差を置いて手拍子が始まったのですから、ここも <, which >とするのが正しいでしょう。He was rushed to the hospital and put in a little room which had dust all over the bed.彼は病院に緊急搬送され、ベッド一面に埃が積もっている小さな部屋に収容されました。= He was rushed to the hospital and put in a little room, which had dust all over the bed.彼は病院に緊急搬送され、小さな部屋に収容されましたが、そこはベッド一面に埃が積もっていました。*限定的な意味合いが薄く、room に関する単純な追加説明と見倣す事が出来ます。*コンマを付けずに限定性の強い意味合いだと解釈すると、他に綺麗な部屋が有ったのにわざわざ汚れた部屋に彼は押し込まれた、の意味にも読めます。My left ankle which I broke last year is still giving me trouble.昨年に折った僕の左のカカトはまだ問題を抱えているんだ。*制限用法と解釈すると、では健康な別の左のカカトもあるのかと問われる可能性は(飽くまで)理屈の上からは成立します。常識のセンからはあり得ませんが。My left ankle, which I broke last year, is still giving me trouble.僕の左のカカトは、去年折ったんだけど、まだ問題を抱えているんだ。*コンマを入れるのが矢張り正しいでしょう。*この例も、マユー あき氏に倣うと、昨年に折ってしまったんだよ、との背景を強く説明する為に(関係代名詞制限用法の<記述的用法>)、コンマ無しで myleft anjkle に強く接続しさせていると解釈も出来そうです。*制限用法と非制限用法との中間的なニュアンスの英文ですね。*特にうるさいことを云わなければ、上の2文はいずれも意味が等しく通じます。************************************************上に採りあげたの様な表記上の揺れも確実に存在しており、制限用法と非制限用法の区別が付けられないケースも実際存在します。*僅かな識別マーカーとしてコンマ1つの違いで2者を区別し、意味に大きな違いがあり得ると騒ぐ英語の発想が、そもそも安直過ぎる、のではと塾長は素朴な疑問を禁じ得ません。*コンマの有無で日本語訳の文章が全く変わって仕舞う事実が、極めて奇妙な現象であり、実際、英語 native は日本語の様な他言語に於いてそこまでの大きな違いを生むとまでは想像すらしていない筈です。*彼らにとっては、語順のままに制限と非制限の文章を読み下して理解するに違いはなく、そこにコンマの有無をどう解釈するか程度の次元の話になります。*コンマの有無を騒ぎ立てる日英間の温度差はだいぶ異なる様には感じます。*日本語の構造が、コンマの有無の違いを更に強調してしまう効果は確実にあるでしょうね。*中尾俊夫・児馬修 編著 『歴史的にさぐる現代の英文法』 の、2.3.5.2.7 制限的 vs. 非制限的役割、の項に、「まして古い時代の英語では、ある関係節が R(= restrictive ) であるか A (= appositive) であるかを決定するのはかなり困難なことである。イントネーションは実証不可能であるし、写本の句読点は気随的であってよるべき規準とならないからである。」とあります。*コンマ使用に関しては、現在に於いても<気随的な>揺れ動きが見られる模様ですね。使う使わないが、native 自身明確且つ厳密な規準を持たないのでしょう。*制限法 vs. 非制限法とは、多義的なニュアンスを持ち得る、或る意味、<成立途上>の英語表現法の1つなのではと正直感じます。*この2つの区別には、 native の解説者含めて事大主義的で、強調し過ぎではないかと塾長は感じますね。*分詞構文などと同様に、意味の曖昧性が完全には排除出来ません。 |
||
 |
 |
https://www.youtube.com/watch?v=apBUEsF7mrw
前回に続き再掲します。
関係詞節の間違いはやめよう![Which & That] mmmEnglish 2019/07/19
最後にいずれが正しいかを問う例文では native でも断言出来ないものも登場し
ますが、その場合は文脈依存で制限か非制限かを問うものになりますね。
制限用法では that を使い、非制限用法では which を用いて解説していますが、
これも簡潔明快で一定の合理性があると感じます。
https://www.youtube.com/watch?v=yG63ApHlhP4
The Chicago Manual of Style: More than a Century of Style
The University of Chicago 2011/11/11
Now in its 16th edition, The Chicago Manual of Style is the must-have reference
for everyone who works with words. On November 8th, a panel of expertsconvened
at International House to discuss both the history of this authoritative text andits
relevance in an era where instantaneous global publication is only a tap, text, or
tweet away. Audience participation was encouraged via live polling on matters of
usage and style and submitting comments and questions via Twitter. Thediscussion
was moderated by Alison Cuddy, host of WBEZ's award-winning news magazineEight
Forty-Eight. Panelists included:
第16版を迎えた『シカゴ・マニュアル・オブ・スタイル』は、言葉に関わるすべての人にとって
必須の参考書である。11月8日、専門家パネルがインターナショナル・ハウスに集結し、この
権威あるテキストの歴史と、瞬時に世界へ発信できる時代におけるその意義について議論し
た。使用法やスタイルに関するライブ投票やTwitterを通じたコメント・質問の投稿により、聴
衆の参加が促された。討論はWBEZの受賞歴あるニュース番組『エイト・フォーティー・エイト』
の司会者アリソン・カディが進行を担当。パネリストは以下の通り: (以下略)
現在では18版 The Chicago Manual Of Style 18th Edition 2025 が世に出ています。
ペーパーバックで2600円程度(アマゾン価格です。)英文で物書をする者にとっては必携
の書物でしょう。尤もその見解に必ずしも従うべきものではないでしょうけれど。また、自然
科学系の論文執筆に際して、その目的に真に叶うかどうか、と言うところですね。
 |
 |
|
制限用法と非制限用法とで関係代名詞を異にすべきかの議論*『シカゴ・マニュアル・オブ・スタイル』 第16版のような多くのアメリカのスタイルガイドでは、一般的に制限関係節では which を避けることを推奨しています。*この規定的な「ルール」は1851年にグールド・ブラウンによって提案されたものですが、 1926年にはH.W.ファウラーによって支持され、彼はこう述べています:「もし作家が that を定義的な(制限的な)関係代名詞とみなし、which を非定義的な関係代名詞とみなすことに同意するならば、明瞭さと容易さの両方で多くの利点があるだろう。*一方、スタンフォード大学の言語学者アーノルド・ズウィッキーは、言語学者は一般的に制限関係詞節で which を使わないというルール案を「実に愚かな考え」とみなしている、と述べています。*実際のところ、余程 formal な英文でもない限り、現状では制限用法の関係代名詞は全て that で記述して構いません。*制限用法は全て that で済ませてしまい、非制限用法は、which, when, where を利用する、これでOKと言う次第で、non-native には有り難いスタイルだとも言えます。中尾俊夫・児馬修 編著 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館書店 1990年の、2.3.5関係代名詞の項に、「that は18世紀までは最も普通に用いられる関係詞であった。圧倒的に制限節と共起することが多いが、非制限節にも用いられる。ME同様前置詞の後ろに来ることは許されない。16-7世紀では有生・無生いずれの先行詞とも共起する。」とあり、that を先行詞の種類に拠って様々に分化させて来た流れが元に戻りつつある様にも見えます。*現状に於いて、that を適宜、who, which, whom, when, where, etc. に使い分ける事が、formal であるとされますが、上記の風潮は英語が平易化-或いは原点回帰-して来ていると言えるのかも知れません。 |
||
 |
 |