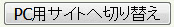英文読解から入試まで 完全マンツーマン指導
https://dictionary.cambridge.org/ja/dictionary/english/
塾長のコラム 2025年11月5日
 |
 |
|
関係詞8 |
||
2025年11月5日 (以下2026年1月12日追記) 皆様、KVC Tokyo 英語塾 塾長 藤野 健です。 少し前に分詞構文について解説しましたが、そこでは分詞構文が従属接続詞、等位接続詞、或いは非接続用法の関係詞(=関係代名詞、関係形容詞、関係副詞など)を利用しての書き換えが適宜可能である事を述べました。いずれも1つの文(主文)に対して、別の情報を加える、併記する用法ですが、考えて見ると少なくとも英語とは、ダラダラと何かの文言を付け加えるのが好きな一面のある言語であることが分かります。しかし、人間の脳の認知機能からは一つの発想に対してあれこれ付け加えるには理解の限度が有り、当然乍ら際限なく文言を加えて行くことは出来ません。<節度>が求められると言うことになります。分詞構文についても然りなのですが、複数の文章を<短縮して繋ぎ合わせる>と言葉の経済に資する上に、<何だか端整で知的な雰囲気も纏えて>カッコいい、の発想自体は特に悪いものではありませんが、1つの文にては単純な1つの事実のみを述べるのが矢張り本来のあるべき姿なのだろうと塾長は考えます。複数情報を繋ぎ合わせる際に、主文に対して、どの文言が付け加えの部分であるのかを示す標識、即ちマーカーの類いを接続詞と言うのですが、関係詞はその1つになります。 まぁ、文章同士をくっつけて<関係させる>際に利用される語のことを関係詞と呼称するのですが、広い意味での接続詞の仲間の1つになります。従属接続詞、等位接続詞を利用して付け加える文構造、即ち従属接続節、等位接続節(独立節とも言う)は、飽くまで主文全体に付加情報を与えるものであるのに対し、主文の中の特定の名詞や主文が主張する想念(これは1つのモノ扱いになります)をキメ打ちして追加情報を<貼り付ける>、強い或いは比較的強い接着剤の働きをするのが関係詞です。この意味で形容詞として機能するもの故、関係詞が構成する節、即ち関詞詞節 relative clauses は形容詞節と呼称出来ます。 モノの形容に関してですが、日本語ではモノの形容語句は名詞の前に置く一方、英語では極く短い文言は別として、長い構造は後置修飾させます。これ故、日本語で解釈するには返り点読みを余儀なくされ、特に初学者は頭を抱えるに至りますし、実際そのまま愚直に!訳したところで意味が取れないなどと却って苦情を言われてしまい兼ねません。この返り点読みを止めさせ、英文を語順のままに理解させるべく、巷ではスラッシュリーディング法が良い、同時通訳的者を倣え(これは当塾長の考え)などと主張されますが、要は、そのまま意味を頭に input しつつ英文を読み下すのが合理的だ、との指導法になりますね。 この様な英文解釈、リーディング上の技法面にも触れつつ、関係詞-関係代名詞、関係形容詞、関係副詞などが有ります-を文法面と意味用法面から含めてザッと一通り見て行きましょう。関係詞の構文上の理解は容易ゆえ、個々の用法や注意点を列挙する形がメインとなりますが、これまでの知識の整理がてら読み進めてみて下さい。損はしない筈です。その第8回目となります。 英国ケンブリッジ英語辞典並びに Collins 英語辞典の用例を主に参考に解説を加えて行きます。https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/whathttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/whathttps://en.wikipedia.org/wiki/English_relative_clauseshttps://en.wikipedia.org/wiki/Conjunction_(grammar)#Subordinating_conjunctionshttps://ja.wikipedia.org/wiki/関係詞https://en.wikipedia.org/wiki/Relativizer*これらに引用されている文献を参照すると更に詳細な学説が得られます。https://www.thoughtco.com/zero-relative-pronoun-1692623https://www.thoughtco.com/zero-or-bare-infinitive-1692621『試験に出る英文法』 森一郎、青春出版社、1971年 第4章 関係代名詞・関係副詞 pp.58-78『チャート式 英文解釈』 鈴木進、数研出版、昭和51年、第2編文の構造上よりの解釈 第3章2 形容詞節 pp.132-168『チャート式 英文法』 荒木良治、数研出版、昭和62年、第3章 5関係代名詞pp.103-11 第5章 3関係副詞 pp.164-168これらの基本的構成並びに(難解な)例文を幾つか参考にしていますが、塾長なりの視点から批判的検討を加え、また一部、より現代的な、或いはより正しい明確な表現となる様、書き換えたものも併記しています。 |
||
 |
 |
https://www.youtube.com/watch?v=cMddWW-mvWc
The Relative Pronouns 'What' and 'Whose' in English
Central School of English 2021/01/19
what を関係代名詞として扱っている動画はこれぐらいしか見付かりませんでした。
英英辞書などを紐解いても単なる代名詞 pronoun 扱いされる例が多いですね。
ここでは、what とは when we don't mention what we are describing 今描写
していることを口にしない時に使うものとして説明していますが、これは要するに
ボカシ表現と云いたいことかと思いますが、疑問詞の what の意味<なに?>に
引きずられ過ぎた片手落ちの解釈でしょう。what は先行詞込みの関係代名詞と
して the thing(s) that, anything that, all that, that which, thosewhich な
どの意味を持ちますが、これを先行詞+関係代名詞とし明確に把握する本邦の
英文法指導に一定の合理性を見ます。native の解説とて玉石混淆な訳です。
 |
 |
|
融合関係代名詞 (Fused RelativePronoun)*本邦の学習参考書等には記述の無い用語ですが、英語には、自由関係構文、融合関係構文、或いは名詞関係構文と呼ばれる構文形式があります。*これは、簡単に言えば、先行詞+関係詞を一語で表す(=融合する)事の出来る語を用いた、先行詞+関係節の塊 (これは名詞節として機能します)のことを指します。*先行詞+関係詞を一語で表す語、のことを、文法学者等により用語の不統一はありますが、融合関係代名詞、或いは複合関係代名詞と呼称します。*2つが合体して融合した語ですので、意味不明の<複合>よりは<融合>を使うべきだろうと塾長は考えますね。*学習参考書などでは、who, which, what に -ever をつけた形を複合関係代名詞 Compound Relative Pronoun と呼称しているものが寧ろ一般的ですが、これは狭義の融合関係代名詞に相当します。*これらの語に関しては次回コラムにて扱います。*そもそも複合関係代名詞の用語ですら native には理解不能な非一般的な言葉の模様で、youtube 動画などで検索しても、この用語で解説を行うものは、日本人とインド人のものばかりとなります。*ネタ元の英文法本がおそらくは同じものであり、古典的な、(少なくとも英語学習黎明期にあっては)定評あったものを採用し、日本とインドの英語指導が兄弟関係になっているのではないかと推測します。*融合関係構文の例として挙げますが、What he did was clearly impossible.彼がしたことは明らかに不可能だった。ここに於いて、what he did = the thing that he did ですので、what = the thing that であり、先行詞と関係代名詞 that が融合していると見做せます。*英語には、what、whatever、whoever など、「融合している」関係代名詞が数多くあります。*これらの語は、他に元からの疑問詞として機能もしますし、譲歩節を形成することもできます。*以下、個別に順次説明を加えて行きましょう。what*what は the thing(s) that, anything that, all that,that which, those which などの意味を持ちます。*英語の辞書を見ても、what が先行詞を含んだ関係代名詞であるとの記述は少なく、単なる代名詞 pronoun 扱いされています。*従って、先行詞を含んだ関係代名詞として what の用法を理解する遣り方は、ほぼ本邦固有の英文法である可能性があります。*しかし、何を言おうとしているのか分かりにくい多くの英英辞典等の説明書きの羅列より、本邦の解釈の仕方の方が余程合理的に感じますね。*native としては、疑問詞の what <何だ?>の意味に引きずられ、<何だかまだ不明のもの、未定のもの>との感覚で what を把握してしまい、先行詞+関係代名詞としの合理的な理解に届かない場合も多いのでは無いかと塾長は考えます。*意味としては、「...するもの」または「...すること」を表します。*what は節の中で主語、目的語、補語の働きを取れますし、what 節全体も名詞節ですので、名詞として主語、目的語、補語になることが出来ます。主語としてWhat you say is true.君が言うことは本当である。ここで、what は say の目的語であると同時に, is 以下の主語になっています。What he said must be true.彼が言った(ところの)ことは真実であるに違いありません。直接目的語としてDo what you want to do.自分がやりたいことをやれ。ここに、what は 後ろの do の目的語、また what youwant to do は文頭の Do の目的語になっています。He said what everyone expected he would (say).彼は皆の期待通りの事を言った。But that is not what you promised me !だがそれは約束がちがう。cf. 動詞 promise は単音節語ではありませんが、例外的に SVOO型 を取れます。*詳細は、https://www.kensvetblog.net/column/202509/20250920/ をご覧下さい。補語としてHis father has made him what he is.彼の父は彼を彼が (いま)あるところのものにした→彼の今日あるのは父のおかげです。註:1.what は普通「人」には用いませんが、上の例文や次のような場合は「人」を指しています。She is just what I was expecting.彼女は私の思っていた通りの人だ。He is not what he used to be.彼は嘗ての彼ではない。2.what は ask, wonder のような、相手に尋ねたり疑問の意味を持つ動詞のあとに続く場合は疑問詞ですが、そうでない場合は関係詞になります。*疑問詞の場合は what を強く発音します。*内容が確定しているならブツ扱いの what、不確定なら質問扱いの what になりますね。I asked him what he had found.私は彼に何を見つけたかを訊いた。 [疑問詞]= I asked him, "What did you find?"He gave me what he had found.彼は見つけたものを私にくれた。 [関係詞]= He gave me the thing that he had found.who(以下2026年1月12日追記)*先行詞を含む用法が過去には who にも存在しました。*現在では融合関係代名詞の用法は who にはなく、正統的な文法書でもそれとして扱われることは全くありません。*時々、日本のどこぞの辞書には先行詞込みの who の記述があることを盾に取り、初学者相手に得意然と示す者も見受られ、問題だと感じますので、ここに正しい事を述べる次第です。Oxford English Dictionary 2nd. editio のwho の項に以下の記述が見られます:As compound relative in the nominative, of persons (less freq. a person): The persons (or person) that. arch. (Chiefly a latinism; esp. in there are who... = L. Sunt qui...主格の複合関係詞として、人(より稀に一人の人)を指す:その人(または人々)。古語(主にラテン語の影響;特に there are who... = L. Sunt qui...の用法において)以下用例の一部:1627 J. Doughty Disc. Div. Myst. (1628) 20 There are who hold no art or science to be extant, which [etc.].現存する芸術や科学を一切認めない者たちがいる、それらが[以下略]。1644 Milton Judgem. Bucer To Parlt. B 4 b, If thir own works be not thought sufficient to defend them, there livs yet who will be ready..to debate.. this matter.もし彼ら自身の著作が彼らを擁護するのに十分でないと考えられるなら、この問題を議論する用意のある者がまだ生きている。1656 Earl of Monmouth tr. Boccalini's Advts. fr. Parnass. ii. xxiv. 262 Through the ingratitude of who commands [It. di chi domanda].1656 モンマス伯爵訳 ボッカリーニ『パルナッソスからの勧告』ii. xxiv. 262 [It. di chi domanda] 命令する者の恩知らずゆえに。1713 Tickell Poems, To Addison, on Cato 36 Whothink like Romans, could like Romans fight.1713 ティッケル『詩集』アディソンへ、カトーについて 36 ローマ人のように考える者は、ローマ人のように戦うこともできた。1805 Wordsw. Ode to Duty ii, There are who asknot if thine eye Be on them.1805 ワーズワース 義務への頌歌 ii, 汝の目が彼らに向けられているか問わぬ者らもまたいる。1871 Browning Pr. Hohenstiel-Schwangau 1007 He should know, sitting on the throne, how tastes Life to who sweeps the doorway.1871 ブラウニング『ホーエンシュティール=シュヴァンガウの牧師』1007 彼は玉座に坐りながら、門を掃く者の人生が如何なる味かを知るべきである。*who = the persons (or person) that の意味で利用されており、who 以下が名詞節を構成して、主語、補語、前置詞の目的語などとして利用されていたことが理解出来ます。*現行では、He is not what he used to be. 彼は嘗ての彼では無い、などの様に、who は用いずに人を表す場合でも what を使用して補語として利用するのが正しいとされます。*He is not who he was. の類いの例文が、自身の愛用する英和辞典?に出ているからと言って、過去の経緯も知らずに正しい表現だと言い張る者も実際散見されますが、不文だと判断して下さい。 |
||
 |
 |
https://www.youtube.com/watch?v=1cGo_vc0Qig
ネイティブは A is to B what C is to D. の構文を理解できるか?
OLP 2021/02/06
ここの what を as に換えると一層理解は容易かと思いますが、what を使った
慣用表現はいずれも平易な定型的文句しか有りません。この動画作成者氏が、
こんな堅い表現ネイティブは使うのか?と記していますが、塾長には一体何が
堅い表現なのか不思議に思いました。というよりか、簡潔平易な表現に感じます。
しかしこの様に native に直接疑問をぶつける、或いは現在ではchatGPT に
尋ねるなどするのも良い遣り方だと思います。学習指導要綱に凝り固まって汲々
としている英語教員や塾講師などは答えられず、さりげなく逃げ出すでしょうね。
 |
 |
|
what の慣用的用法what is better/ worseHe went to the meeting and, what was worse,insisted on speaking.彼は会合に出掛けて行ったが、更に悪いことには話をするのだと言ってきかなかった。He is handsome, clever, and what is better still,very rich.彼は美男子で利口で、更に良いことには,非常にお金持ちです。=He is handsome, clever, and what is better still isthat he is very rich.*これを縮めたものと理解出来ます。He failed in the entrance examination, and whatmade the matter worse, he fell ill.彼は入学試験に失敗した。そして事態をいっそう悪くしたことには,病気になった。what with...what withWhat with hunger, and (what with) fatigue, he fell down.飢えやら疲労やらで彼は倒れた。*informal な口語的表現になります。what is calledShe is what is called 〔what we call〕 "a societylady."彼女はいわゆる「社交婦人」です。He is what is called a modern boy.彼はモダン・ボーイと 呼ばれるところのものだ→彼はいわゆるモダン・ボーイです。----------------------------------------------------A is to B what C is to D.*A : B = X : Y " いう 比 例 を表わします。*ここの what は、<特別な意味を持つ what の用法>の1つで、OED 2nd ed. what の項目に以下の様な説明並びに用例が掲載されています。Expressing parallel relation or correspondence(with to in principal clause and in relative clause).1673ュ4 Grew Anat. Pl. iii. (1682) 127 And what the Mouth is, to an Animal; that the Root is to a Plant.1732 Berkeley Alciphr. iv. ァ21 Intellect is to themind what sight is to the body.1853 Ruskin Stones Venice III. iv. ァ11 What theelm and oak are to England, the olive is to Italy.1914 Month Dec. 608 Jingoism is to truepatriotism what bigotry is to true religion.並列関係または対応関係を表す(主節及び関係節に於いて to を伴い)。1673年4月 グロウ解剖学図譜 iii. (1682) 127 動物にとっての口が、植物にとっての根であるように。1732 バークレー『アルキフォーン』iv. ァ21 知性は心にとって、視覚が身体にとってのそれである。1853 ラスキン『ヴェネツィアの石』III. iv. ァ11 楡と樫がイングランドにとってのそれであるように、オリーブはイタリアにとってのそれである。1914 『マンス』12月号 608 軍国主義は真の愛国心にとって、偏狭が真の宗教に対するそれである。Water is to fish what air is to man.水が魚に対する関係は空気が人間に対する関係と同じです。= Water is to fish as air is to humans.*what の代わりに as が用いられることがあります。= Water against fish is the same as air against man.= Just as water is essential for fish, air isessential for humans.*The relationship between water and fish issimilar to that between air and man.と長々と記すよりはずっと簡潔な表現になりますね。Reading is to the mind what food is to the body.読書が精神に対するのは食物が身体に対するが如くです。*****************************************試しに chatGPT に以下の質問をぶつけてみました:Q. Is the expression "A is to B what C is to D"used normally in formal of informal sentences?A. The expression“A is to B what C is to D” is a comparative construction that draws an analogy between two relationships.For example: “Reading is to the mind whatexercise is to the body.”Use in formal vs. informal contexts:・ Formal: Yes, it is often used in formal writing and speech (essays, lectures, academic texts, philosophy, literature). It has a slightly elevated, rhetorical tone.・ Informal: It can also appear in informal contexts, but it may sound a bit “bookish” or stylized compared to simpler alternatives (e.g., “Reading helps the mind the wayexercise helps the body”).Summary:More common in formal/serious contexts, where analogies are drawn with precision.Less common in casual speech, though still understandable.質問:「AはBに対して、CがDに対してである」という表現は、正式な文と非公式な文のどちらで通常使われますか?答え:. 「AはBに対して、CがDに対してである」という表現は、二つの関係を類推する比較構文です。例:「読書は心にとって、運動が身体にとってであるものと同じである。」正式な文脈と非公式な文脈での使用:・ フォーマル:はい、正式な文章やスピーチ(論文、講義、学術書、哲学、文学)で頻繁に使用されます。やや高尚で修辞的な響きがあります。・ インフォーマル:非公式な文脈でも見られますが、より単純な表現(例:「読書は運動が体に役立つように心に役立つ」)と比べると、やや「堅苦しい」または様式化された印象を与える可能性があります。要約より formal・真剣な文脈で一般的であり、精密な比喩に用いられます。カジュアルな会話ではあまり使われないが、それでも理解は可能です。と、出ました。*ヘタな native に訊くより余程タメになりますね。*AI が普及すると、巷の英会話スクールの大方も、<実際の度胸漬け>の練習以外には不要になりそうです・・・。*皆さんもどしどし AI を利用されると刺激になるでしょうし、学校英語レベルの質問に対しては大方適格な答えが返ると考えて良さそうです。*但し、適格な質問を行う技量と同時に、得られた回答の妥当性を見分ける為の一定以上の英語力は矢張り必要でしょう。**************************************** |
||
 |
 |