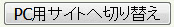英文読解から入試まで 完全マンツーマン指導
https://dictionary.cambridge.org/ja/dictionary/english/
塾長のコラム 2025年11月15日
 |
 |
|
関係詞10 |
||
2025年11月15日 (2025年12月16日追記) 皆様、KVC Tokyo 英語塾 塾長 藤野 健です。 少し前に分詞構文について解説しましたが、そこでは分詞構文が従属接続詞、等位接続詞、或いは非接続用法の関係詞(=関係代名詞、関係形容詞、関係副詞など)を利用しての書き換えが適宜可能である事を述べました。いずれも1つの文(主文)に対して、別の情報を加える、併記する用法ですが、考えて見ると少なくとも英語とは、ダラダラと何かの文言を付け加えるのが好きな一面のある言語であることが分かります。しかし、人間の脳の認知機能からは一つの発想に対してあれこれ付け加えるには理解の限度が有り、当然乍ら際限なく文言を加えて行くことは出来ません。<節度>が求められると言うことになります。分詞構文についても然りなのですが、複数の文章を<短縮して繋ぎ合わせる>と言葉の経済に資する上に、<何だか端整で知的な雰囲気も纏えて>カッコいい、の発想自体は特に悪いものではありませんが、1つの文にては単純な1つの事実のみを述べるのが矢張り本来のあるべき姿なのだろうと塾長は考えます。複数情報を繋ぎ合わせる際に、主文に対して、どの文言が付け加えの部分であるのかを示す標識、即ちマーカーの類いを接続詞と言うのですが、関係詞はその1つになります。 まぁ、文章同士をくっつけて<関係させる>際に利用される語のことを関係詞と呼称するのですが、広い意味での接続詞の仲間の1つになります。従属接続詞、等位接続詞を利用して付け加える文構造、即ち従属接続節、等位接続節(独立節とも言う)は、飽くまで主文全体に付加情報を与えるものであるのに対し、主文の中の特定の名詞や主文が主張する想念(これは1つのモノ扱いになります)をキメ打ちして追加情報を<貼り付ける>、強い或いは比較的強い接着剤の働きをするのが関係詞です。この意味で形容詞として機能するもの故、関係詞が構成する節、即ち関詞詞節 relative clauses は形容詞節と呼称出来ます。 モノの形容に関してですが、日本語ではモノの形容語句は名詞の前に置く一方、英語では極く短い文言は別として、長い構造は後置修飾させます。これ故、日本語で解釈するには返り点読みを余儀なくされ、特に初学者は頭を抱えるに至りますし、実際そのまま愚直に!訳したところで意味が取れないなどと却って苦情を言われてしまい兼ねません。この返り点読みを止めさせ、英文を語順のままに理解させるべく、巷ではスラッシュリーディング法が良い、同時通訳的者を倣え(これは当塾長の考え)などと主張されますが、要は、そのまま意味を頭に input しつつ英文を読み下すのが合理的だ、との指導法になりますね。 この様な英文解釈、リーディング上の技法面にも触れつつ、関係詞-関係代名詞、関係形容詞、関係副詞などが有ります-を文法面と意味用法面から含めてザッと一通り見て行きましょう。関係詞の構文上の理解は容易ゆえ、個々の用法や注意点を列挙する形がメインとなりますが、これまでの知識の整理がてら読み進めてみて下さい。損はしない筈です。その第10回目となります。 英国ケンブリッジ英語辞典並びに Collins 英語辞典の用例を主に参考に解説を加えて行きます。https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/whichhttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/whichhttps://en.wikipedia.org/wiki/English_relative_clauseshttps://en.wikipedia.org/wiki/Conjunction_(grammar)#Subordinating_conjunctionshttps://ja.wikipedia.org/wiki/関係詞https://en.wikipedia.org/wiki/Relativizer*これらに引用されている文献を参照すると更に詳細な学説が得られます。https://www.thoughtco.com/zero-relative-pronoun-1692623https://www.thoughtco.com/zero-or-bare-infinitive-1692621『試験に出る英文法』 森一郎、青春出版社、1971年 第4章 関係代名詞・関係副詞 pp.58-78『チャート式 英文解釈』 鈴木進、数研出版、昭和51年、第2編文の構造上よりの解釈 第3章2 形容詞節 pp.132-168『チャート式 英文法』 荒木良治、数研出版、昭和62年、第3章 5関係代名詞pp.103-11 第5章 3関係副詞 pp.164-168これらの基本的構成並びに(難解な)例文を幾つか参考にしていますが、塾長なりの視点から批判的検討を加え、また一部、より現代的な、或いはより正しい明確な表現となる様、書き換えたものも併記しています。 |
||
 |
 |
https://www.youtube.com/watch?v=zvddzzLtTx0
Prepositions in Relative Clauses Oxford English Now 2023/09/29
前置詞+関係詞の用法につて詳細且つ網羅的に解説が為されます。
 |
 |
|
Relative pronoun as the object of apreposition前置詞の目的語としての関係代名詞*前置詞の目的語としての関係代名詞は、制限節でも非制限節でも共に、しばしば登場します。*以下用例は、Prepositions in Relative ClausesOxford English Nowhttps://www.youtube.com/watch?v=zvddzzLtTx0 から主にお借りしています。制限節Jack is the boy with whom Jenny fell in love.ジャックはジェニーが恋に落ちた少年だ。非制限節Yesterday, Jenny met Jack, for whom she no longer has any feelings.昨日、ジェニーはジャックに会ったが、彼に対しては最早何の感情も抱いていない。*関係節の前置詞が前に置かれる (fronted)場合、目的格の whom または which のみが使用されます。*関係節の前に前置詞が置かれる表現は、より formal ですが、堅苦しい印象を与えもします。*前置詞が関係代名詞 that の前に置かれることは全くありません。*通常、前置詞を後置する場合は関係代名詞としてthat を使いますが、informal に近い用法になります。*前置詞が関係詞の文末に置かれることは特に口語に於いては普通のことであり、更に関係代名詞が省略される事もあります。*関係代名詞が省略される場合、前置詞は必ず後置されます。Jack is the boy whom/ that Jenny fell in love with.Jack is the boy (whom/ that) Jenny fell in love with.ジャックはジェニーが恋に落ちた少年です。The boy to whom I spoke was his brother.私が話しかけた少年は彼の兄弟であった。=The boy (whom) I spoke to was his brother.= The boy (that) I spoke to was his brother.Jack is the boy with whom Jenny fell in love.Jack is the boy whom Jenny fell in love with.Jack is the boy (that) Jenny fell in love with.ジャックはジェニーが恋に落ちた少年である"△ Jack is boy who Jenny fell in love with.*whom の代わりに who を使うのは、インフォーマルな文体でもしばしば見られますが、進んでの使用は控えて下さい。。He was reading an old book the cover of which was torn out.彼はその表紙がすり切れた古い本を読んでいました。=He was reading an old book of which the cover was torn out.=He was reading an old book whose cover was torn out. (この文が普通の表現です)*必ず関係代名詞の前に置かねばならない以下の前置詞(句)があります。after, because of, before, below, besides, duringThe sixties was a period during which many people wore flowerly clothes.1960年代は、多くの人が花柄の服を着ていた時代だった。Midnight is the time after which students are not allowed to leave.深夜零時とは、それ以降学生が外出を許可されない時間である。A deadline is the time before which you must complete smething.締切とは、その前に何かを完了しなければならない期限である。*phrasal verb に利用される前置詞は、1つの塊としての機能を持ちますので、分離してはならず、必ず関係節の末に置いたままにします。To lose weight there were certain food (which) he had to cut back on.= To lose weight there were certain food (which)he had to reduce..体重を減らすために、彼が減らす必要があった特定の食べ物があった。×To lose weight there were certain food onwhich he had to cut back..cf. cut back on = to reduceShe is the actress (who/ whom) I always looked up to.= She is the actress (who/ whom) I always admired.彼女は私がいつも憧れていた女優だ。× She is the actress to whom I always looked up.cf. look up to = to respect and admire 憧れる |
||
 |
 |
https://www.youtube.com/watch?v=guiOQZ0NhuY
Object Relative Clauses with Prepositions Illustration 2016/07/12
2つの文をスンナリと関係代名詞構文に合成できるか演習して下さい。
 |
 |
|
連鎖関係(代名詞)節*<I think that he is kind. のような S + V + that 節>を関係節化したものが連鎖関係(代名詞)節と呼ばれることがあります。*連鎖関係節とは concatenated relative clause の訳語ですが、別段連鎖の語をここにわざわざ使用するのも奇妙です。*毎度の英文法用語の恣意的な呼称でしょう。それを言葉通りに和訳する本邦の英語学者も芸が不足する様に感じます。*学習参考書などでは、関係詞の直後に I think などが挿入された構造と見做して解説されますが、この解説法で何ら問題も有りません。*平易に、関係代名詞節へのSV挿入用法、とでも呼べば足ります。cf. concatenate = to link or join together, esp in achain or series 鎖の様に繋ぎ合わせるThe man who I believed was my friend deceived me.私が私の友人であると信じていた男が私を欺しました。= I believed the man was my friend. But he deceived me.She is a girl who I know is proficient in English.彼女は、英語が達者であるということを私が知っている(ところの) 少女です。= She is a girl who is proficient in English, and I know that.*挿入されたI believed や I know をカッコ に括ってつまみ出せば who を whom にしてマズいことが分かるでしょう。I haven't met a boy who you know is the brightest student ever.あなたがこれまでで最高に賢い学生だと思っている男の子には、私は会ったことがない。= You know that the boy is the brightest student ever, but I haven't met him..*ここの you know = you think ですね。註: この例文の who は is の主語であるため、whom とするのは文法的に誤りです。しかし、実際には who を know の目的語と見なして whom とする、いわゆる 「関係詞牽引」 現象が起きることも多いですね。関係代名詞二重限定用法*1つの先行詞に対して、2つの関係節が掛かる構造になります。*形式的には、1つの先行詞に対して3つ以上の関係詞が掛かる構造も作れますが、実際には見た事が有りません。*2つの関係代名詞節の内、意味の重点は後の節にあり、前の関係代名詞節は挿入句的に軽く訳します。*この構造では第2の関係節の頭の関係代名詞は省略されません。これはそれが関係節であるマーカとして機能するからです。*その意味で、上に述べた連鎖関係(代名詞)節の用法にも類似しており、実際、構文的にも類似していて非常に紛らわしいです。I haven't met a boy (that) you know who is the brightest student ever.君が知っている中で、これまでで一番優秀な生徒という男の子には会ったことがない。*この文は、以下の<合体>であると解説されるのですが、I haven't met a boy that you know. 且つ I haven't met a boy who is the brightest student ever.しかし、you know who is the brightest student ever を一塊に理解するのが普通のことでしょう。実際、*I haven't met a boy.且つ You know he is the brightest student everこれを1文にすると、I haven't met a boy (that) you know who is the brightest student ever.と同じ文になります。*即ち、この文の you know 部分は、連鎖関係(代名詞)節の I know などと大差無い文言であることが理解出来ます。*試しにこの who を除去すると、I haven't met a boy that you know who is the brightest student ever.→I haven't met a boy that you know is the brightest student ever.これは関係代名詞への挿入用法になってしまいます。There is no one that I know who deserves to marry you.私が知っている人であなたと結婚す価値のある人はいません。≒ There is no one who I know deserves to marry you.あなたと結婚す価値のあると私が知る者はいません。= None of people I know deserves to marry you.語順通りにサッと理解するのがコツですね。然るに、別の表現では I know などより重みがあり、There are plenty of things I can do that I have not done yet.私ができることでまだ私がしていないことがたくさんあります。= There are plenty of things I can do. + There are plenty of things I have not done yet.= Plenty of thing I can do I have not done yet. (倒置)= I have not done yet plenty of thing I can do (元に戻して)There were some things the tutor said that I didn’t understand.家庭教師が言ったことの中には、私が理解できなかったものもあった。= There were some things the tutor said. + Therewere some things that I didn’t understand.= Some of the things the tutor said I didn'tunderstand.= I didn't understand some of the things the tutorsaid.これを例えばThe tutor said there were some things that I did not understand.とすると、家庭教師は、私が理解していないことがいくつかあると言った。と、意味が違って来てしまいますね。There were some things I knew that I didn’t understand.知ってはいるが理解出来て居ないものが幾つかある。= Some of the things I knew I didn't understand.= I didn't understand some of the things I knew.*二重限定用法にて二重の返り点読みをすると時に混乱します。*語順通りに読み下して理解するのがコツですね。*最後は一番重要である後ろの文言を前に持って行きます。 |
||
 |
 |